「寒四郎」(かんしろう)とは、
「寒の入り」から4日目のことで、
今年、令和6(2024)年の「寒四郎」は、
1月9日[火曜日]になります。
寒さが最も厳しい時期に注意を促すためか、
「麦づくり」の厄日とされます。

この日の天候で
その年の収穫を占う習わしがあり、
「彼岸太郎 に八専次郎 、土用三郎 、寒四郎 」
と言って、
彼岸の一日目、八専の二日目、土用の三日目、
そして「寒四郎」(かんしろう)のこの日に
晴れるとその年は「豊作」、
雨や雪なら「凶作」とされました。

寒太郎(かんたろう)
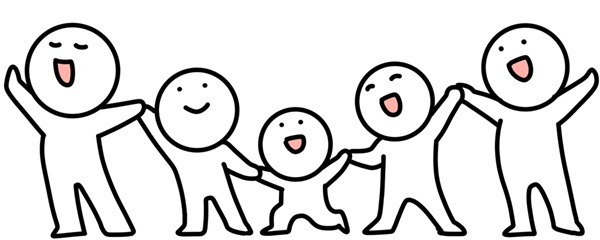
一部の地域では、「寒の入り」である
「小寒」のことを擬人化して、
「寒太郎」(かんたろう)と呼びます。
「輩行」とは「一族のうち同世代の者」という意味で、通常は兄弟のことを言う。輩行名は「輩行」のうちの
男の子の兄弟の長幼の序列(=出生順)を表した
太郎(一郎)、次郎(二郎)、三郎・・・
といった名前のことを
「輩行名」(はいこうめい)と言います。
嵯峨天皇が第一皇子以下に対して
太郎、次郎、三郎といった
幼名を授けたことに由来するそうです。
そこから転じて「寒の季節の初日」を
「寒太郎」(かんたろう)と呼ぶようになった
ようです。

因みに童謡の『北風小僧の寒太郎』は、
『みんなのうた』の楽曲としては
最も再放送が多い曲『北風小僧の寒太郎』は、
昭和49(1974)年12月に堺正章さんの歌で
登場しました。
当初は、東京都の実写風景をバックに
アニメの寒太郎を合成していましたが、
昭和52(1977)年頃からは全編アニメとなり、
堺正章さん、北島三郎さんなどが歌ったものが
放映され続けています。
また、小学校の音楽の教科書にも
何度か掲載されました。
寒九(かんく)

更に「寒の入り」から9日目は
「寒九」(かんく)と言います。
「寒九」は「寒四郎」とは逆で、
雨が降るとそれは「恵みの雨」と考えられて、
「豊作」になると言われています。


