
雑節の「入梅」(にゅうばい)は、
暦の上での「梅雨入りの日」のことで、
令和7(2025)年の雑節「入梅」の日は
6月11日0時24分になります。
入梅
「入梅」(にゅうばい・ついり・つゆいり)とは、
「梅雨入り」の時期に設定された
「雑節」のことです。
「入梅」と「梅雨入り」は
似たような意味の言葉ですが、
「入梅」は「暦の上」での呼び名で、
「梅雨入り」は
気象条件が実際に揃った際の呼び名です。
「入梅」は、太陽黄経が80°の時を指し、
毎年6月11日か12日頃で、
「立春」から数えて135日目に当たります。
農家にとって梅雨入りの時期を知ることは、
田植えの日を決める上でも重要でした。
昔は、現在のように
気象予報が発達していなかったため、
江戸時代に目安として
暦の上で「入梅」を設けたとされます。
「入梅」の時期は二十四節気の
「芒種」後の最初の「壬」(みずのえ)の日に、
「小暑」の後に来る「壬」(みずのえ)の日を
「梅雨明け」としました。
これは「壬」(みずのえ)が、
陰陽五行説で「水の気の強い性格」であり、
「水」と縁があるためです。
「入梅」の起源

「入梅」の由来や起源は、
はっきりと分かってはいませんが、
どうして「梅」という言葉が使われるように
なったのでしょうか。
梅の実が熟す頃の「雨」
梅の実が熟する頃に雨季に入ることから、
「入梅」と言われるようになったという
説です。
確かに6月は梅の実が熟して、
スーパーや八百屋などで
梅の実が並ぶ時期でもあります。
昔の人はこうした梅の実を見ることで、
「そろそろ梅雨だな」と
感じ取っていたのかもしれません。
カビが生えやすい時期の「雨」
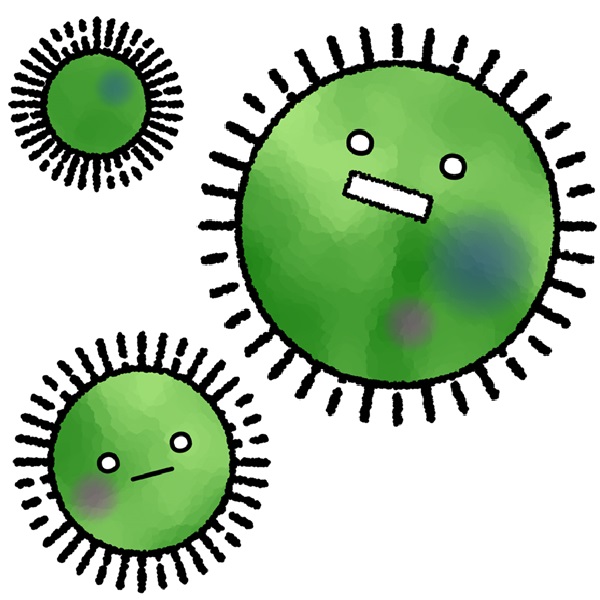
この頃は湿度が高くなって
「黴」(かび)が生えやすくなるため
「黴雨」(ばいう)と呼んでいましたが、
「カビでは語感が良くないので、
同じ読みで季節に合った「梅」の字を使い
「梅雨」になったという説です。
毎日降る「雨」
「毎」「日」のように雨が降るので
「梅」という字が使われたという説です。
「梅雨」を「つゆ」と
呼ぶようになった由来
「梅雨」という言葉が伝わる以前は
「五月雨」(さみだれ)と言ったそうです。
「梅雨」を「つゆ」と呼ぶようになったのは、
- 「露」(つゆ)から連想した
- 梅の実が熟す時期だから
「つはる」から連想した - 梅の実が熟し潰れる時期だから
「潰ゆ(つゆ)」と関連つけた - カビのせいで物が損なわれる
「費ゆ(つひゆ)」から連想した
といった説があります。
関連
走り梅雨(はしりつゆ)
梅雨の言葉
七十二候「梅子黄」
梅干し
「梅雨入り」宣言

暦の上では、
雑節の「入梅」の日からが「梅雨」ですが、
実際の「梅雨入り」は
気象庁がその日までの天気経過と
1週間先までの天気の見通しを判断して
各地方予報中枢官署が「梅雨入り宣言」を
します。
天気図では、「梅雨前線」が日本付近に
停滞前線として現れる頃となっています。
梅雨入り・梅雨明けを発表する各気象台
- 仙台管区気象台 (東北地方)
- 東京管区気象台 (関東地方)
- 新潟地方気象台 (北陸地方)
- 名古屋地方気象台(東海地方)
- 大阪管区気象台 (近畿地方)
- 広島地方気象台 (中国地方)
- 高松地方気象台 (四国地方)
- 福岡管区気象台 (九州北部地方)
- 鹿児島地方気象台(九州南部地方)
- 沖縄気象台 (沖縄地方)
気象庁が「梅雨入り」「梅雨明け」の
発表をするようになったのは、
昭和39(1964)年からと
そんなに古い話ではありません。
昭和61(1986)年からは
「梅雨入り・明けの発表」は
業務として位置づけられました。
平成7(1995)年以降は、
「梅雨」が季節現象であることを
明確にするために、
数日の幅を持った「期間」として
表現するようになりました。
なお、「梅雨」の季節が過ぎた後に
再び検討して、
秋頃に「梅雨入りの日」が
修正される事もあります。
