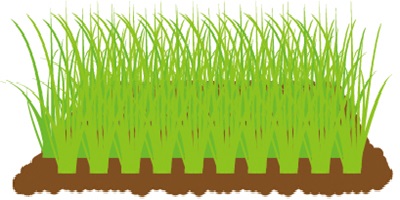
「苗代」(なわしろ) に水を引いて、
「種籾」(たねもみ) を蒔く時期を
「苗代時」(なわしろどき) と言います。
種籾を蒔くのは地域によって異なりますが、「八十八夜」前後の晩春の時期に当たります。
この時期に思わぬ寒い日があり、
これを「苗代寒」(なわしろかん) と言います。
「苗代」(なわしろ) とは、「田植え」前に
稲の苗を育てるための場所のことです。
田んぼとは別の場所で、
そこに水はけと保水性の良い土を用意して、
2~3週間水に浸しておいた「種籾」(たねもみ) を
蒔いて育てます。
良質な苗を育てることは、
後の栽培期間における作物の生育に直結し、
最終的な秋の収穫を高める重要な作業です。

種籾は、まず塩水に入れて
浮いた悪い籾を取り除く「種選び」をし、
催芽を促すために「種俵」(たねだわら) に入れて、
2~3週間程、井戸や池や小川などに浸けた
ものです。
この種を浸けるための井戸や池などを
「種井」(たない) 「種池」(たねいけ)
「種桶」(たねおけ) と言います。

農業は自然に左右されますから、
種籾を苗代に蒔く「種蒔き」の時期も
自然の営みに合わせて行う地方が多く、
山に現れる雪形(雪の模様)の出現や形、
春に先駆けて咲く辛夷 (こぶし) をの開花を
種蒔きの目安としています。

苗代に種籾を蒔いたら、この種籾を守るために
「種案山子」(たねかかし) を設置します。
苗代に水が満ちている時はいいのですが、
油断して水が無くなると、途端に
雀達の集中攻撃を受けてしまうからです。
ただ案山子の効果も最初だけで、その後は
雀も慣れっこになってしまうのだそうですが。
なお苗代に種籾を蒔く際、
苗代田の「水口」で
田の神を祀り豊作を祈る祭り
「水口祭」(みなぐちまつり) を行います。
餅を搗き、苗代粥を炊いて祝い、
苗代の真ん中に木の枝、竹などを立てて、
田の神を祀ります。
揃った苗の上を風が渡り、
種案山子が立っている光景などは、
晩春らしい風景です。
さあ苗が育ったら、いよいよ初夏の
「田植え」が始まります。


