
「菊人形」は、頭や手足はリアルな人形で、
胴体を中小菊の花で着飾られた
等身大の人形です。
江戸後期、江戸の染井や巣鴨周辺で流行し、
幕末からは本郷の団子坂で盛んに行われました。
その後は、鉄道会社の観光事業ともなって、
全国に広がりました。
「菊人形」の始まり
「菊人形」(きくにんぎょう) は、
頭部と手足こそリアルな人形ですが、
衣装は菊の花によって出来ているものです。
菊の栽培ブーム
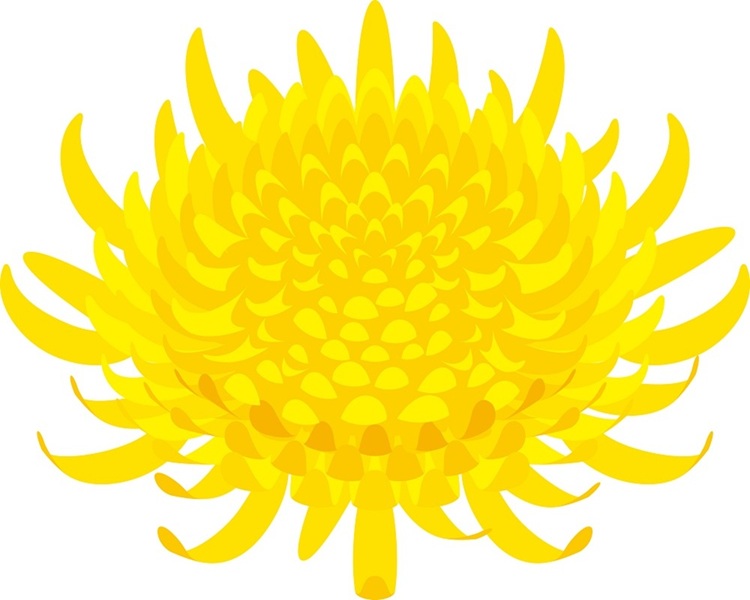
江戸時代に入り、菊の栽培熱が
庶民の間でも高まるようになると、
菊の品種改良が行われ、種類も豊富になり、
「菊合わせ」「菊大会」と呼ばれる
品評会が各地で行なわれるようになりました。
特に巣鴨には、「菊見」に押し掛ける人々で
長蛇の列ができ、
80余りの植木屋と100軒もの出店で
賑わったという記録が残されています。

染井の植木職人村でも
菊の栽培や品種改良が盛んに行われました。
品種改良でどんどん種類が増え、
それを欲しがる人のために
『新菊苗割代附帳』や『京新菊苗割帳』など、
今でいう苗のカタログまで出版されたそう
です。
菊細工(造り菊)

江戸中期になると、巣鴨・染井の植木職人らは
一本から多数の花を咲かせる
「咲分の菊」や「千輪咲き」といった
「花壇づくり」を始め、
これらを菊の作り物を庭に置いて、
一般にも開放したことから、
多くの人々が見物に訪れました。
「菊人形」の始まり

その後一時衰退するも、文化9(1812)年、
染井で評判となったことをきっかけに、
鶴や象などの鳥獣、富士山などの風景、
宝舟などの縁起物、汐汲などの物語を、
小菊で形作った「菊細工 (造り菊)」といった
技巧を凝らしたものが作られるようになり、
更には人を模した
「菊人形」へと発展していきました。
天保15(1844)年に巣鴨の霊感院に奉納された
細工が「菊人形」の始まりと言われています。
その後「菊人形」は、安政3(1856)年には、
浅草寺で80数種の大輪の菊の見世物があったり、
文久元(1861)年には、千駄木の「団子坂」に、
忠臣蔵狂言の菊人形が登場するなど、
神社仏閣の奉納物として飾られる奉納細工から
歌舞伎の場面や戦争などの場面を再現した
独立した興行へと変わっていきました。
菊人形展は「団子坂」
その後、幕末から明治にかけて
「菊人形展」の中心は、
江戸・東京郊外の景勝地の一つであった
現在の文京区千駄木の「団子坂」に移りました。
「団子坂」の地名の由来は、
「団子のような石の多い坂だった」とか、
「昔、団子を売る茶店があった」などの
説があります。
またかつては、坂上から
「東京湾」の入江まで望むことが出来たため「潮見坂」とも呼ばれていました。
始まり
安政3(1856)年に、巣鴨より移住してきていた
植木屋(後の「植梅」)が、
明治8(1875)年に制作した「造り菊」が
評判となったことから、
翌年から東京府から正式に許可を受けて、
木戸銭を取って正式に興行として認められると
更に隆盛を極め、
東京の秋の始めを彩る一大見世物イベントに
成長しました。
因みに木戸銭=菊見料は3厘でした。
最盛期
明治20年代から30年代になると、
「団子坂」での興行は最盛期を迎えます。
明治17(1884)年、雨の日でも鑑賞出来るように、
筵を張った粗末な小屋が作られますが、
明治25(1892)年からは本格的な建物になり、
回転したり、せり上がる舞台など、
歌舞伎的な仕掛けや、背景の装飾も施され、
現在の「菊人形展」の基礎が形作られました。
評判の歌舞伎狂言を題材にしたものが
多く見られた他、
日清戦争や磐梯山噴火などの時事物、
舌切り雀など昔話・時代劇など
テーマは多岐に渡りました。
それを「植惣」「種半」「植梅」「植重」の
四大園を含む20軒以上が
「団子坂」沿いや周辺に軒を連ねて、
趣向を凝らして競い合うようになったと
言われています。
「菊人形」は人形師によって作られ、
大勢の見物人を前に出来栄えを競いました。
中でも安本亀八や山本福松といった
「生人形師」(いきにんぎょうし) の作った頭が
呼び物となりました。
頭や手足も生人形職人が作ったものは
今では文化財とされています。
また菊の花は日が経つと枯れるため、
5日程で取り替えられたそうです。
こうして「菊人形展」は
「団子坂」との評判が高まり、
「団子坂」もいつしか「菊見坂」と
呼ばれるようになりました。
衰退
賑わいを見せた「団子坂の菊人形展」も、
明治末期頃になると衰退していきました。
明治42(1909)年に名古屋から進出してきた
「黄花園」(こうかえん) が「両国国技館」で
ショービジネス化した「菊人形展」を開催し、
大成功を収めたからです。
明治42(1909)年5月31日、東京・墨田区両国の
本所回向院の境内に初代の「両国国技館」が
完成しました。
建築家の辰野金吾が設計を手掛け、
日本初となるドーム型鉄骨板張の洋風建築
建物です。
設立委員長の板垣退助が、日本の国技である
相撲を行う場所として「國技館」と命名した
そうです。
そうして国技館の興行が人気を浚った結果、
「団子坂」から客足が遠のき、
明治44(1911)年が最後の興行となり、
明治の終わりとともに姿を消してしまい
ました。
菊見せんべい総本店
「菊見せんべい総本店」は、明治8年創業の
団子坂にある煎餅屋です。
団子坂にあった菊人形展に集まった人の
手土産として誕生した「菊見せんべい」は、
店先で煎餅を焼いている(当時)のが好評で、
人気を集めました。
森鴎外や高村光雲・光太郎親子も
好んで食べていたようです。
黄花園(こうかえん)
「黄花園」とは
「黄花園」(こうかえん) は、
愛知郡高畑村(現中川区高畑)生まれの
奥村伊三郎 (おくむら いさぶろう) が
明治27(1894)年に愛知県名古屋市大須にある
万松寺境内に開いた菊人形展示場です。
奥村は元々は菊の栽培師でしたが、
明治35(1902)年には三河吉浜(高浜市吉浜)の
細工人形師を「黄花園」の菊師として雇って、
精巧で豪華な菊人形に仕上げ、
更に電気仕掛けの菊人形を導入したり、
活動写真や大掛かりな舞台装置を取り入れる等
菊人形をショービジネス化して、
東京両国、大阪枚方、伊勢、博多など
全国的に展開した「菊人形余興」は大盛況で、
当時の盛り場大須の象徴的存在となりました。
「両国国技館」での興行

明治42(1909)年5月に完成した国技館では
同年秋に奥村の「黄花園」の手で
「菊人形」が催され、大成功を収めました。
乃村工藝社

しかし「黄花園」は2年で、
引き継いだ岐阜の「浅野菊楽園」も
早々に手を引いたため、
大正2(1913)年前後からは、
「乃村工藝社」が手掛けるようになります。
「乃村工藝社」は、明治25(1892)年に
乃村泰資が香川県高松で芝居の大道具業として
創業し、明治末頃からは拠点を東京へ移し、
大正年間には興行主として博覧会に参入して
いました。
そして当時、大衆の娯楽として人気のあった
「菊人形興行」に
歌舞伎の「段返し」(だんがえし) からヒントを得、
大規模な装置と仕掛けを使った新たな演出を
加えました。
段返し(だんがえし)
物語の進展に応じて
舞台の下の奈落からの「せり上げ」や
天井からの「吊り下げ」、「廻り舞台」、
舞台袖の「書割」(かきわり) を駆使して
幕間なく一瞬のうちに場面転換する仕組み。
乃村泰資は、「両国国技館」の興行では、
21回場面が変わる「21段返し」を
実現させました。
他にも、弁士の「語り」、天井の「花提灯」、
踊子による華やかな「踊り」など、
様々な趣向が凝らされました。
また「福引」もあり、
福引に当たると、白粉・化粧・化粧クリームのいずれかがもらえたそうです。
全国各地に広がる菊人形
その後「菊人形」展は、
菊人形専門のプロデューサーが
興行を取り仕切る大規模なレジャーへと
発展し、全国各地へ広まりました。
大阪では、京阪電鉄、阪神電鉄、南海鉄道、
高野山鉄道など鉄道会社が、
自社の宣伝・集客のために
「菊人形」展を開催しました。
愛知県では、昭和2(1927)年に
愛知電気鉄道(現・名鉄名古屋本線)の
神宮前駅と吉田駅(現・豊橋駅)の間が全通すると
愛電の往復乗車券に
「黄花園」の入場券を付けた切符が
販売されるようになり、
名古屋電気鉄道犬山駅や名鉄岐阜駅からの
同様の切符も販売されるようになった。
なお昭和11(1936)年には、
大須の「黄花園」は閉園となりました。
戦争激化のため一時中断されましたが、
戦後に復活。
東京や大阪の私鉄沿線では
昭和50年代半ばまで、秋恒例の呼び物で、
首都圏では多摩川園や谷津遊園などが、
関西圏では「ひらかた大菊人形」が
有名でした。
但し、東京、大阪とも、
菊人形に生きた菊花を織り込む職人「菊師」や
菊人形用に品種改良した、特殊な小菊
「人形菊」の栽培者の高齢化、後継者不足で、
催事の継続が難しくなったとのこともあり、
以前ほど菊人形工業は少なくなっている
ようです。
「ひらかた大菊人形」も平成17(2005)年の秋、
96年の歴史の幕を閉じました。

ただ、全国的に見ればまだまだ盛況で、
例えば「日本最大の菊の祭典」という
福島県の二本松市、あるいは山形県の南陽市、
茨城県の笠間市、福井県の越前市(旧武生市)
などでの「菊人形」は、今も賑わっています。

谷中菊まつり
「団子坂」の菊人形は廃れてしまいましたが、
昭和59(1984)年に大圓寺境内にて
「谷中菊まつり」として復活しています。
今年令和7(2025)年は10月11日、12日に
菊人形の展示が行われる他、薪舞 (たきぎまい)、
菊市などが催されます。
文京菊まつり
(湯島天神菊まつり)
文京区は区の花である菊をPRする目的で、
昭和54(1979)年より、湯島天神で
始めました。
令和7(2025)年は11月1日(土)から23日(祝・日)まで
開催される予定になっています。
