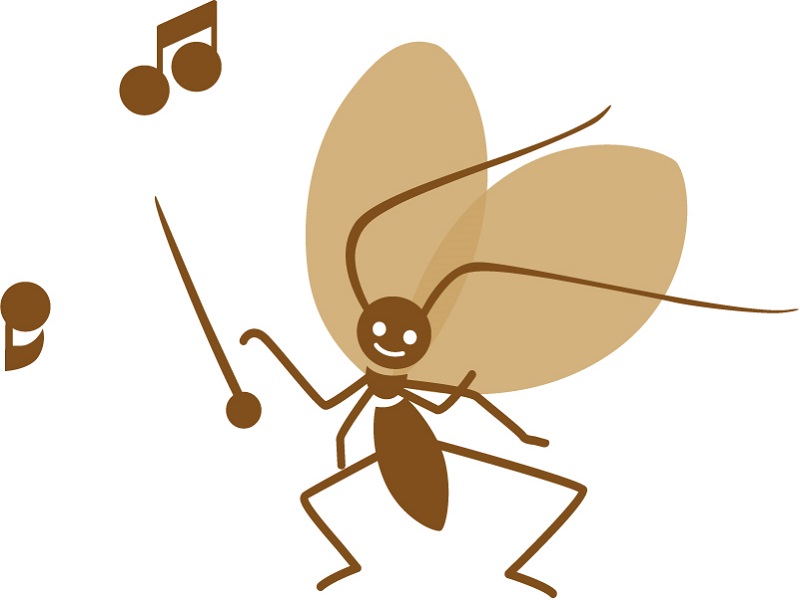
歳時記において、
「花」と言えば「桜」、
「月」と言えば「秋の月」というように、
「虫」と言えば「秋に鳴く虫」を指します。
虫の音(むしのね)

「虫の音」(むしのね)とは虫の鳴く声、
取り分け秋に鳴く虫の声のことを言います。
秋に鳴く虫には、松虫、鈴虫、蟋蟀など、
様々います。
なお、鳴くのはオスだけで、
二枚の前翅(ぜんし)を擦り合わせて
音を出します。
なお、虫が鳴く気温というのは、
15度から30度の間と言われており、
気温が15度を下回ると鳴かないのだそうです。
秋の虫の声
「秋」の風情を表す「虫」の言葉は
沢山あります。
キリギリス科

・螽 斯(きりぎりす):チョン・ギース
・馬 追(うまおい) :スイッチョ
・轡 虫(くつわむし):ガチャガチャ
・露 虫(つゆむし) :ピチチピチチ
コオロギ科

・蟋 蟀(こおろぎ) :
・閻魔蟋蟀 (えんまこおろぎ):コロコロコロリーリー
・三角蟋蟀(みつかどこおろぎ):キチキチキチ
・綴刺蟋蟀(つづれさせこおろぎ):リリリリ
・草雲雀(くさひばり):フィリリリ、キリリリリ
・松 虫(まつむし) :チンチロリン
・鉦 叩(かねたたき):チンチンチン
・邯 鄲(かんたん) :ルルルルルー
スズムシ科
・鈴 虫(すずむし) :リーンリーン
スズムシ科の昆虫で、名前の通り
「リーン リーン」と鈴の音のように鳴き、
その美しい鳴き声から 「鳴く虫の王」 と言われ、別名は「月鈴子」(げつれいし) と言います。
森の中や田畑の脇の暗い草地に生息し、
夜行性で夜に下草の間で鳴き声を上げます。
蟋蟀(こおろぎ)

「蟋蟀」(こおろぎ) というのは
コオロギ科の虫の総称で、
日本には30種類程生息しています。
別名は「ちちろ」「ちちろ虫」「つづれさせ」
などです。
一般的に「コオロギ」と言う場合は、
「エンマコオロギ」を指すことが多いです。
『万葉集』の時代には、「蟋蟀」(こおろぎ) は
秋に鳴く虫の総称だったようです。
夕月夜 心もしのに白露の
置くこの庭に 蟋蟀鳴くも
置くこの庭に 蟋蟀鳴くも
月の明るい夕べに、白露の降りている
この庭でコオロギが鳴いている、
それを聞くと私の心もしんみりとする。
この庭でコオロギが鳴いている、
それを聞くと私の心もしんみりとする。
秋風の 寒く吹くなへ 我が宿の
浅茅が本に こほろぎ鳴くも
浅茅が本に こほろぎ鳴くも
秋風が寒く吹くにつれて、私の庭の
茅萱(ちがや)のもとで、コオロギが鳴いている。
茅萱(ちがや)のもとで、コオロギが鳴いている。
庭草に 村雨降りて こほろぎの
鳴く声聞けば 秋づきにけり
鳴く声聞けば 秋づきにけり
庭の草に村雨が降って、コオロギの鳴く声を
聞くと、秋の訪れを感じる。
聞くと、秋の訪れを感じる。
こほろぎの 待ち喜ぶる秋の
夜を寝る 験なし 枕と我れは
夜を寝る 験なし 枕と我れは
コオロギが待ち望んでいた秋の夜なのに
寝る甲斐もないよ、枕と私だけでは。
寝る甲斐もないよ、枕と私だけでは。
虫聞き(むしきき)
昔は、秋に鳴く「虫の声」に、
秋の訪れや深まりを感じたり、
涼しさや寂しさを感じたりしてきました。
これは、日本人独特の感性だと言います。
夕暮れ時に、野や山に出掛けて、
虫の声に耳を澄ませて楽しむことを、
「虫聞き」と言います。
平安時代には、既に「虫の声を愛でる文化」が
ありました。
『源氏物語』の中にも、「花見」と同じく
宮廷生活の文化として描かれています。
江戸時代には、「花見」「月見」「菊見」「雪見」
そして「虫聞き」が庶民の「五つの風流」と
されました。
江戸時代の「虫聞き」の名所と言えば、
広尾や道灌山(現在の鶯谷から西日暮里の丘)、
それから上野の不忍池などでした。
家族で酒肴を持って出掛けたという
記録が残っています。(『江戸名所図鑑』)
現在でも、東京都の「向島百花園」や
国宝「彦根城」や京都の寺院などでは、
「お月見」や「茶会」と合わせて
「虫聞き」が行われています。
虫選び

平安時代、強の相野谷鳥辺野などに赴き、
松虫や鈴虫などの鳴く虫を捕えては、
籠に入れて持ち帰る「虫狩り」や、
捕ってきた虫を宮中に放ち、
その音を楽しむ「虫選び」、
また、捕った虫の姿や鳴き声を競い合う、
「虫合わせ」に興じたそうです。
虫の季語
虫時雨(むししぐれ)

秋の夜に賑やかに響く虫の音を指す言葉に、
「虫時雨」(むししぐれ)というものがあります。
沢山の虫が一斉に鳴く声が、ザーッと降って、
サッと上がる「時雨」のようであることから
来ているようです。
「時雨」が降る毎に冬が深まってゆくように、
「虫時雨」が聞こえる毎に、
秋もその深さを増していくようです。
虫達のシンフォニーが心地良いですね。
虫の闇
秋の夜闇に「虫の声」だけ聞こえ、
闇がより暗く感じられること。
昼の虫
虫の多くは夜間に鳴きますが、
時に昼間にも鳴いている虫がいます。
残る虫
晩秋の季語です。
秋が立った頃から
美しい音色を奏でていた虫達も、
晩秋になると随分減ってきます。
それでも、か細い声で鳴いている虫達は
「残る虫」と呼ばれてきました。
「虫時雨」が虫の盛りの頃としたら、
「残る虫」は終わりかけですが、
懸命に鳴く声には、美しい響きが宿っています。
虫の声は日本人にしか聞こえない?

虫の「声」は、日本人には聞こえるのに、
外国人には聞こえないと言われています。
東京医科歯科大学の角田忠信教授が
ご自身の体験に基づき研究をされた結果、
次のような説を導き出しました。

人間の脳は右脳と左脳とに分かれ、
右脳は「音楽脳」とも呼ばれ、
音楽や機械音、雑音を処理しています。
一方、左脳は「言語脳」と呼ばれ、
人間の話す声の理解など、
論理的知的な処理を受け持ちます。
この機能は日本人も西洋人も一緒ですが、
「虫の音」をどちらの脳で聴くかという点で
違いが見つかったそうです。
西洋人は「虫の音」を右脳の「音楽脳」で処理し、
いつもの騒々しい雑音だと慣れてしまえば、
意識に上らなくなってしまいます。
一方日本人は、「虫の音」を
左脳の「言語脳」で処理し、
「虫の声」として聞いていることを
突き止めました。
これは、世界でも日本人とポリネシア人だけに見られる特徴で、Chineseや韓国人は
同じ東アジア人であっても西洋型だそうです。

「虫の音」と同様に、
日本人が左脳で聴く音には、
「波」「風」「雨の音」「小川のせせらぎ」
などがあるそうです。

日本人はよく情緒的と言われますが、
自然の音を雑音として認識するのではなく、
自然から発せられている言葉として認識してる
からなのでしょうか。


