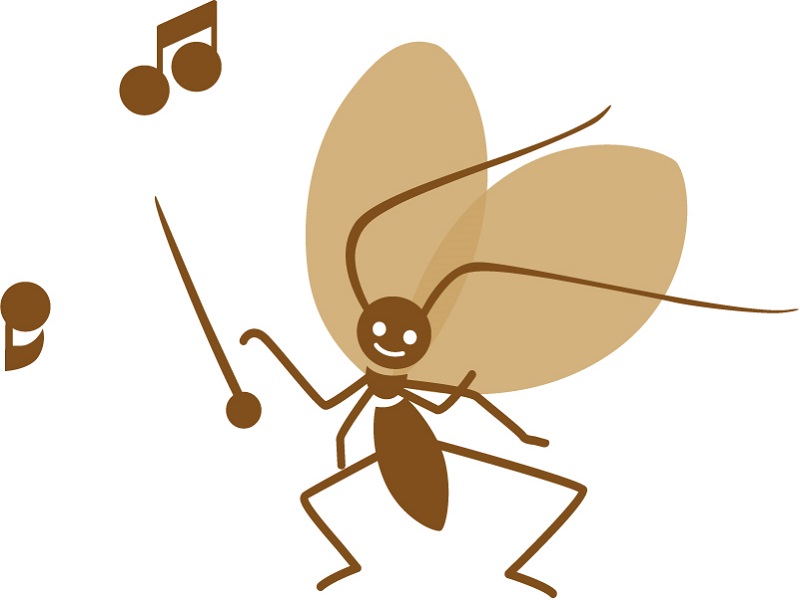
「きりぎりすとにあり」
と読みます。
戸口で秋の虫が鳴き始める頃となりました。
「キリギリス」とありますが、
昔は「蟋蟀 (コオロギ)」のことを
「キリギリス」と呼び、
秋に鳴く虫の総称としていました。
キリギリスは、古くから日本人によって
観賞用に飼育されてきました。
そのため、江戸時代から大正にかけて、
蟋蟀(こおろぎ)、鈴虫(すずむし)、
松虫(まつむし)、轡虫(くつわむし)、
蜩(ひぐらし)などを
美しい籠に入れて売り歩く
「虫売り」という行商ビジネスもありました。
コオロギ科以外で、
唯一商品価値を持つ「鳴く虫」であった
「キリギリス」は、
竹製のカゴ「ギスかご」に入れて販売され、
そのカゴが縁側や店先に吊るされて
キリギリスが鳴き声を響かせ、
お盆になると、飼い置いた虫を放ちました。
1980年代初頭までは、
キリギリスがデパートや夜店で販売され、
大きな河川敷や野原では、小銭稼ぎの
「ギッチョ採りのおじさん」が見られましたが、
いつの間にか消えてしまいました。
ところで、「キリギリス」は
別名を「機織り虫」と言います。
昔は、秋の夜長、聞きなしした虫の声に
励まされながら、針仕事に勤しみました。
声の主は、「ツヅレサセコオロギ」。
リ、リ、リ、リ、リ、・・・と、
一定のリズムで10分も20分も続く鳴き声が、
「肩刺せ、裾刺せ、綴れ刺せ」と
聞こえたのだとか。
「着物の肩や裾に針を刺して、
綴れ(ほころび)を直しておきましょうね。
早くしないと寒さが来ちゃいますよ!」と、
虫達が冬支度を導いてくれたのでしょうか?







