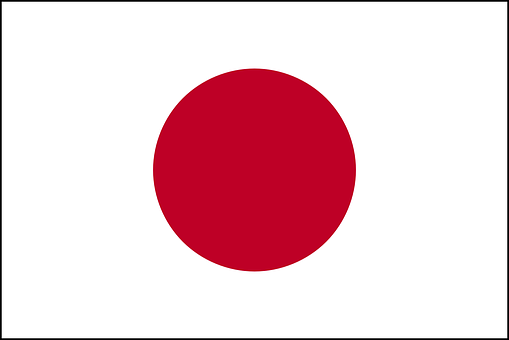4月29日は国民の祝日「昭和の日」です。
「激動の日々を経て、
復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす」日です。
「昭和の日」実現への道

昭和64(1989)年1月7日の昭和天皇崩御の後、
それまで「天皇誕生日」であった4月29日を
「生物学者であり自然を愛した
昭和天皇をしのぶ日」として
「緑の日」とすることとなりました。
しかし、実際に制定された法律では、
「昭和天皇を偲ぶ」という趣旨が
盛り込まれなかったため、
「昭和の日」に改称する法律案が
超党派の国会議員により提出されました。
そして数度の廃案の後、
平成17(2005)年に成立し、
平成19(2007)年より、
4月29日が「昭和の日」、
5月4日が「みどりの日」となりました。
昭和天皇の御生涯

誕生

昭和天皇は、明治34(1901)年4月29日に
皇太子 (当時)・嘉仁親王(後の大正天皇)と
同妃・節子(後の貞明皇后)の第一男子として
東京・青山の東宮御所で御誕生になりました。
御祖父・明治天皇により、
御名を「裕仁」(ひろひと)、
御称号を「迪宮」(みちのみや) と賜りました。
お印は「若竹」(わかたけ)です。
「お印」(おしるし) とは、
皇室の個人が、名前に代わって、
身の回りの品につける印章のことです。
シンボルマークのようなもので、
その人のことを表すサインです。
皇太子、そして摂政に

学習院初等学科第5学年在学中の
明治45(1912)年7月30日、
明治天皇の崩御により、皇太子となられました。
大正3(1914)年より大正10(1921)年まで、
「東宮御学問所」にて学ばれました。
この間、大正5(1916)年11月3日に
「立太子の礼」が行われ、
大正8(1919)年には成年に達し、
5月7日「成年式」が行われました。
大正10(1921)年3月に軍艦香取で出発し、
そこから半年間、欧州ヨーロッパ諸国を巡遊、
見聞を広められました。
これは日本の皇太子の最初の外遊でした。
ところで幼少の頃から病弱だった大正天皇は、
体の不調に悩まされながらも
公務を務められていましたが、
大正9(1920)年には「宮内省」から、
天皇の体調が悪化していることが報じられ、
翌年11月には皇室会議と枢密院により、
「摂政」設置が決議され、
皇太子は摂政に任ぜられました。
大正13(1924)年1月26日には、
久邇宮邦彦 (くにのみやくによし) 王の
第一女子・良子女王(香淳皇后)と
ご結婚になりました。
療養に専念されていた大正天皇でしたが、
大正15(1926)年の年初、風邪がきっかけで、
更に体調を悪化させます。
その後も状態は思わしくなく、
大正15(1926)年12月25日、貞明皇后、
実母の柳原愛子、皇太子夫妻らが見守る中、
享年47で御崩御されました。
第124代の天皇に
大正15(1926)年12月25日、
大正天皇が御崩御されると、
直ちに践祚 (せんそ) の儀式が行われ、
第124代の天皇となられ、
元号が「昭和」と改められました。
なおこの時に天皇は
「一夫一婦制」を守ることを表明されました。
「践祚」(せんそ) とは、
「祚 (くらい) を践 (ふ) む」という意味で、
天皇が皇位の地位を踏みしめる、つまり
皇位に就く=皇位継承を意味します。
先帝が崩御された場合、または譲位によって行われます。
昭和3(1928)年11月10日には
京都御所で「即位の礼」を、
11月14から15日には、
仙洞御所内の御殿跡地に造営した
大嘗宮で「大嘗祭」(だいじょうさい)が
挙行されました。
戦前・戦中

即位前後に天皇が心痛していたのは、
世界の情勢。
そんな渦の中に日本も巻き込まれ、
戦争に引きずられていきます。
天皇はそれらに躊躇を示し、
そのような意見を表明しましたが、最終的には
憲法に従い内閣の決定に従いました。
長く激しい戦いの末、
「ポツダム宣言」受諾か否かという
内閣や軍部内の対立の中で開かれた御前会議で
天皇は「受諾」の意思を表明し、
昭和20(1945)年8月14日、
ポツダム宣言受諾の御聖断を下されました。
翌8月15日の玉音放送は、
天皇の声を国民が聞いた最初となりました。
戦後
昭和天皇が心を痛めていたのは、
自分の臣下であった者が、
戦争犯罪人として裁かれることでした。
「自分が一人引き受けて、退位でもして、
収める訳にはいかないだろうか」と、
木戸内大臣にそう洩らされたそうです。

昭和20(1945)年9月27日、昭和天皇は
在日米国大使館のマッカーサー元帥を訪問。
「全ての決定と行動に対する全責任を
負うものとして私がその人です。
私自身をあなたの代表する諸国の採決に
委ねるためにお尋ねをした」と
述べています。
地方巡幸

占領下で迎えた初めての新年、
昭和21(1946)年の「元旦」は、
昭和天皇の「人間宣言」で始まりました。
そして翌2月からは、
「地方巡幸」を始められました。
戦没者・戦争犠牲者の遺族を労わり、
敗北と飢餓に襲われて絶望の中にある人々に
笑顔をもたらすため、
また戦後復興に励む国民に勇気を与えるために
「人間天皇」は精力的に全国を訪れました。
それは昭和29(1954)年8月の北海道訪問まで
続けられました。
国民と共に

その後も昭和天皇は
沖縄を除く全国を巡幸されました。
沖縄に寄せる昭和天皇の思いは深く、
その願いが叶えられ、昭和62(1987)年、
沖縄へのご訪問を予定していたところ、
病により体調を崩され、中止となって
しまいました。
「思はざる病となりぬ
沖縄をたづねて 果さむつとめありしを」
という御製を残されています。
この思いは現・上皇陛下に受け継がれました。
皇太子時代の昭和50(1975)年7月、
本土復帰の3年後、
妃殿下とともに初めて沖縄をご訪問。
この時、過激派から火炎瓶を投げつけられる
という事件が発生しましたが、以来、
天皇になり御退位されるまでの間、
11回も沖縄を御訪問されました。
昭和25(1950)年以来、
国土緑化運動の中心的な行事である
「全国植樹祭」に、毎春、
香淳皇后と共に御臨席になりました。
また昭和22(1947)年から、
「国民体育大会(現・国民スポーツ大会)」にも
出席されました。

また昭和天皇は相撲を非常に愛好され、
天覧相撲を多く観戦しました。
特に、昭和30(1955)年以降は
国技館で40回も観戦されています。
皇室外交

昭和天皇は、戦後の国際社会への復帰に向け、
積極的に海外を訪問しました。
昭和46(1971)年には、
半世紀ぶりにヨーロッパ諸国、
昭和50(1975)年には米国を、
それぞれ香淳皇后と共に外遊されました。
また日本を訪問する外国首脳と頻繁に会談し、
親睦を深めるなど、皇室外交を展開しました。
日本史上最長の在位記録

昭和天皇は、
昭和元(1926)年から昭和64(1989)年までの
62年在位されました。
これは信頼できる記録が残る
飛鳥時代の推古天皇以降で
最も長い在位期間です。
因みに2番目は明治天皇の45年、
3番目は江戸時代後期の光格天皇の37年です。
昭和51(1976)年11月には、日本武道館で
「天皇在位50年記念式典」が、
昭和61(1986)年には
「天皇在位60年記念式典」が挙行されました。
また在位中に80歳以上の年齢に達した天皇は、
87歳で崩御した昭和天皇と、
85歳で退位された現・上皇陛下のお2人だけだ
ということです。
御崩御
昭和62(1957)年に慢性すい炎で入院、
一時退院されましたが、翌年倒れて再度入院。
昭和64(1989)年1月7日午前6時33分、
十二指腸乳頭周囲腫瘍(腺がん)により、
吹上御所において御崩御 (御歳87) されました。
同月31日に、諡号を「昭和天皇」と定められ
ました。
平成元年2月24日、昭和天皇の「大喪の礼」が
国の儀式として新宿御苑において行われ、
陵は「武蔵野陵」(むさしののみささぎ)と
定められました。
生物学者として
昭和天皇は、ご幼少の頃より、
昆虫や海洋生物に関心を持たれていました。
大正末期頃より余暇をみては、生物学者として
専門的な海洋生物・植物の分類研究を続けられ、
御著書も多数御出版になりました。
📖日本産1新属1新種の記載をともなう
カゴメウミヒドラ科Clathrozonidaeの
ヒドロ虫類の検討(1967年2月)
カゴメウミヒドラ科Clathrozonidaeの
ヒドロ虫類の検討(1967年2月)
📖天草諸島のヒドロ虫類(1969年9月)
📖カゴメウミヒドラClathrozoon wilsoni Spencer
に関する追補(1971年9月)
に関する追補(1971年9月)
📖小笠原諸島のヒドロゾア類(1974年11月)
📖紅海アカバ湾産ヒドロ虫類5種(1977年11月)
📖伊豆大島および新島のヒドロ虫類
(1983年6月)
(1983年6月)
📖パナマ湾産の新ヒドロ虫
Hydractinia bayeri n.sp.ベイヤーウミヒドラ
(1984年6月)
Hydractinia bayeri n.sp.ベイヤーウミヒドラ
(1984年6月)
📖相模湾産ヒドロ虫類(1988年8月)
📖相模湾産ヒドロ虫類 2(1995年12月)
・・・などなど
自然を愛した昭和天皇には、
様々なエピソードが残されています。
学習院初等学科5年生の授業で
カエルの解剖を習ったことから、
帰宅してからトノサマガエルの解剖を行い、
観察後は死骸を箱に入れて庭に埋めて、
「正一位蛙大明神」の称号をお与えになった。

釣った魚は研究のため全て食べる主義で、
「ナマコが食べられるのだから、
ウミウシ(海牛)も食べられるはずだ」と、
葉山御用邸で料理長にウミウシを調理させ、
召し上がった。
ただ後に、
「あまり美味しいものではなかった」と
述べられた。

「雑草という植物はない」と述べられた。