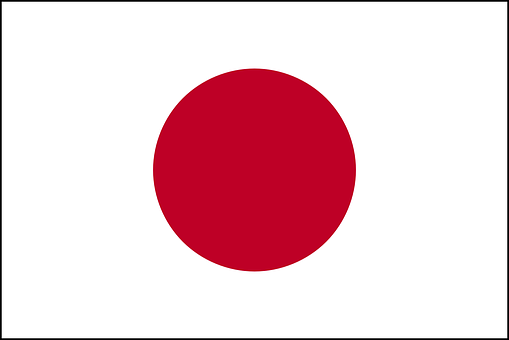「お彼岸」であって先祖を祭る日でした。
またお彼岸に最も近い「戊」の日は、
「社日」として氏子が氏神たる神社に参詣し、
春は「五穀豊穣」を祈り、
秋は実りある「収穫に感謝する」習わしも
ありました。
明治11(1978)年に、
これまでの歴代天皇や主たる皇族の忌日を
春と秋にまとめ奉祀することとなり、
明治41(1908)年9月19日制定の「皇室祭祀令」で
「春季皇霊祭」・「秋季皇霊祭」ともに
大祭に指定されます。
「皇室祭祀令」は、昭和22(1947)年5月2日に
廃止されましたが、宮中では従来通りの
「春季皇霊祭」「秋季皇霊祭」が現在も
行われています。
「春分の日」は「春季皇霊祭」、
「秋分の日」は「秋季皇霊祭」が行われ、
宮中において「祖先を祭る日」になったのを
きっかけとして、祭日とされました。
戦後、昭和23(1948)年に
二つの祝日は残りましたが、国としては、
天皇の御霊のお祀りをする日ではなく、
「春分の日」は
「自然をたたえ生物をいつくしむ」日に、
「秋分の日」は
「祖先をうやまい亡くなった人をしのぶ」日と
法律で定められました。
太陽信仰が「春分の日」に、
浄土信仰が「秋分の日」になったと
言えるのかもしれませんが・・・。