
「土用」とは、
立春、立夏、立秋、立冬の前の
約18日間のことです。
「土用」は季節の変わり目の時期で、
四季に合わせて4回あります。
令和7(2025)年の土用期間
「土用」とは
土用の起源
「五行思想」(ごぎょうしそう)においては、
万物は木、火、土、金、水の
五種類の元素からなるとしていて、
四季は次のように割り当てられています。
- 春=木
- 夏=火
- 秋=金
- 冬=水
そして、それぞれ季節の変わり目には
「土」が割り当てられ、
これを「土用」と言います。

土用にやってはいけないこと
1.土を動かし
土用の期間は土を司る神様である
「土公神」(どくじん) が支配する期間のため、
土に関係することを行うと災いが起こると
されています。
具体的には、
土をいじることや、井戸を掘ること、
家を建てたりすることなどです。
2.新しいこと・場所を移動すること
土用はそれぞれ季節の変わり目に当たるため、
体調を崩しやすい時期でもあります。
転職や就職、結婚や新居購入、旅行など
「新しいこと・場所を移動すること」は
避けたほうがいいとされていたようです。
土用間日
土用期間中には「間日」(かんじつ) と呼ばれる
「土を動かしても大丈夫な日」 があります。
この間日であれば土を司る「土公神」が
天上に行く日で土を離れるため、
土動かしをしても良いとされています。
4つの季節の土用それぞれの間日は
下記となります。
- 令和7(2025)年の土用期間 -
⛄ 冬土用:寅の日、卯の日、巳の日
🌸 春土用:巳の日、丑の日、酉の日
🍉 夏土用:卯の日、辰の日、申の日
🍂 秋土用:未の日[10/29]、
酉の日[10/31]、
亥の日[10/21・11/2]
心と体の不良に気をつけたい期間
「土用」の期間は
ちょうど季節の変わり目に当たるため、
体調不良に気をつけたい期間です。
普段以上に気を付けて行動をしたり、
食事には旬の物を取り入れて、
体に活力を取り入れましょう。

またこの期間は、季節の変化により精神的にも落ち込みやすい時。
気持ちが不安定になる、感傷的になる、
衝動買いをしやすくなるといった
傾向になりやすくなります。
それも季節の変わり目だからと
自覚していると少しラクかもしれません。
ソワソワする時は
無理して突き進もうとせずに休憩を。
ゆっくり足湯やお風呂に浸かるのも、
心を落ち着かせるためにはいいですね。
心身の健康管理にも十分注意して下さい。
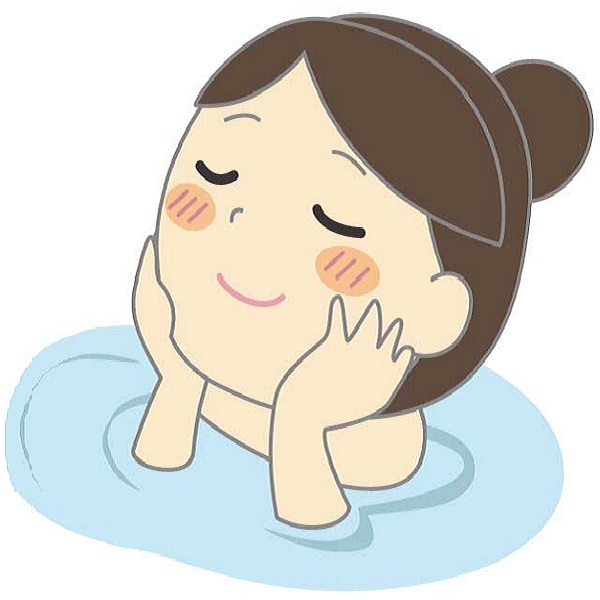
「秋の土用」の期間に
気を付けた方がいいこと
では、「秋の土用」には、具体的に
どんなことに気をつけたらよいのでしょうか?
「秋土用」は、夏に溜まった疲れが
表面化しやすい時期です。
気温差によっても体調を崩しがちです。
「何んとなく調子が悪いかな」と思ったら、
ここで少しだけ休んでみるのも
いいかもしれません。
秋が過ぎれば、今度は寒い冬がやってきます。
喉を痛めたり、咳が止まらなくなったり、
冷えにより体調不良を起こすこともあります。
ですから「秋土用」は、冬に向けて体力を
つけるきっかけとなる時期でもあります。
「秋の土用」に食べるといいもの
「秋の土用」に食べるといいものとは
何でしょうか?
「秋の土用」には、「辰」(たつ)の日に
「た」のつくものとか、「青いもの」を
食べるといいと言われています。
「た」のつく食べ物と言えば、
鯛、大根、大豆、高菜、蛸、卵、
玉ねぎ、タピオカ、鱈、タラコ、
タルト、タンメン・・・。

「青いもの」と言えば、何と言っても
秋に旬を迎える「青魚」です。
サンマを筆頭に、イワシ、サバ、ニシン、
カンパチ、戻りガツオ、太刀魚、オキアジ、
オニアジなどなどは、この時期、
脂が乗って栄養たっぷりです!

こうしたものを食べて、暑い夏の疲れを癒し、
体調を崩しやすい季節の変わり目を乗り切り、
冬に備えようということなのでしょう。



