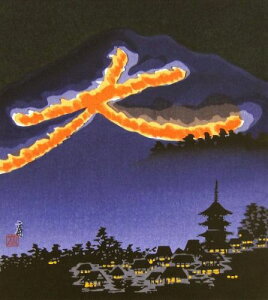「お盆」は、
旧暦7月15日を中心に行われてきた、
祖先の霊(祖霊)をお迎えして、もてなし、
お送りする行事です。
『日本書紀』によると、
古くは推古天皇14年(606年)に
「四月の八日、七月の十五日に
設斎(おがみ)す」とあることから、
その頃には既にお盆の習わしがあったようです。
お盆は、「盂蘭盆会」(うらぼんえ)という
仏教行事であるとともに、
仏教の渡来以前から日本で行われていた
祖先の霊を祭る習わしの名残りでもあり、
両者が合わさったものと言われています。
江戸時代以前は、
お盆は貴族や武士、僧侶などの
上流階級の行事でした。
しかし、江戸時代になると
仏壇や提灯に欠かせないロウソクが
大量生産で安価に取得出来るようになり、
お盆の風習が庶民の間にも広まりました。
お盆は、宗教・宗派や地域によって
独自の発展を見せ、現在の姿に至ります。
「七夕」を始め、京都の「五山の送り火」、
長崎の「精霊流し」などもお盆の行事に
当たります。
お盆の日にちは地方により異なり、
「新暦」の7月13日から16日に行う地方、
1か月ずらして
8月13日から16日に行う「月遅れ盆」の地方、
あるいは今も旧暦の7月13日から16日に行う
「旧盆」の地方があります。
多くの地域では「月遅れ」で行いますが、
「新暦」は関東・北陸・中部などの一部で、
「旧盆」は沖縄や奄美などで行われています。
8月1日にお盆をするところもあります。