
江戸には桜を始めとして、
花見の名所が数多くありましたが、
虫聴きの名所も少なくありませんでした。
特に江戸の虫聴きの名所と言えば、
何と言っても西日暮里駅近くにそびえる
「道灌山」(どうかんやま) でした。
道灌山(どうかんやま)
現在のどの辺り?

「道灌山」(どうかんやま) は、
現在のJR西日暮里駅に隣接する
荒川区西日暮里3丁目~4丁目の辺りになります。
今は開成中学・高校があります。
今は当時の面影はありませんが、
「道灌山」の一部が
「西日暮里公園」となっており、
かつての眺望の良さが味わえるようになって
います。

地名の由来

「道灌山」(どうかんやま) の地名の由来については
2つの説があります。
1つは、谷中の感応寺(現・天王寺)の開基、
関道観と呼ばれた人の屋敷があったところから
この名前がついたという説です。
もう1つは、江戸城を築いた太田道灌の出城が
この地にあったところから付いたという説
です。
江戸でも有数の行楽地
山手台地上野から広がる丘陵地帯の北西端の
最高地点にある「道灌山」は、
江戸時代に入ると、
眺望の良く四季折々の自然が楽しめることから
江戸でも有数の行楽地として発展しました。

また「道灌山」は薬草も豊富で、
90種以上も自生していたそうで、
薬草の採取地としても人気がありました。
「虫聴き」の名所に

風流を好む江戸っ子達は、
夕刻となり日が暮れると、
武士も町人も、男性も女性も連れ立って、
郊外まで足を運んで
虫とともに夕涼みを楽しみました。

初夏の夜には「蛍狩り」、
晩夏から初秋にかけては「虫聴き」です。
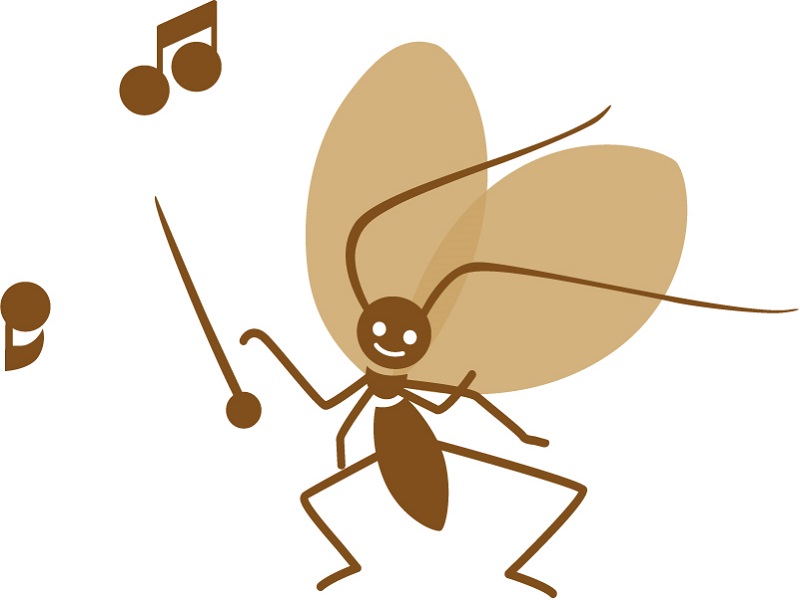
松虫、鈴虫、轡虫 (くつわむし) 、蟋蟀など、
お馴染みの虫の音を夜通しで楽しむために
好んで出掛けました。

その江戸の虫聴きの名所ナンバーワンが
「道灌山」だったのです。
江戸の観光ガイドブックである
『江戸名所図会』にも、
「道灌山聴蟲」という表題で
取り上げられるほどの観光名所でした。

秋の虫の音を楽しむことは、
何も江戸時代に始まったことではなく、
日本古来からの娯楽であり文化でした。
平安時代の『源氏物語』にも、
鈴虫や松虫の音を楽しむ様子が
著されています。

ただ江戸時代は、社会が安定したこともあって
「虫聴き」のような娯楽が
一般庶民に広く流行したのでしょう。
日暮らしの里
元々は「新堀」だった

「日暮里」という地名は、元々は、
新開拓地を意味する「新堀」(にいぼり) だったと
言われています。
「新堀」から「日暮里」へ

新堀(日暮里)には、寛永2(1625)年に
江戸城の鬼門である上野に
「寛永寺」(かんえいじ) が創建されたこと、
また幕府の政策によって
神田周辺から寺院が移転してきたことで、
多くの寺院が建てられました。
寛延年間(1748-51)の頃から
寺院に躑躅が植えられ、江戸名所の1つとなり、
人々は薬草を摘んだり、花見や月見、雪見、
そして秋の虫の音を楽しむようになりました。

文人墨客 (ぶんじんぼっかく) も数多く訪れ、
この辺りにあった、
浄光寺、本行寺、青雲寺は、
文人趣味でそれぞれ
雪見寺、月見寺、花見寺と呼ばれました。
諏方 (すわ) 神社からの眺めは特に素晴らしく、
多くの人が歌や詩に詠んだほどでした。
浮世絵にも当時の美しさが描かれています。

こうしたことからこの一帯は、
「新堀村」からいつしか「日暮里」と
呼ばれるようになりました。

春の桜や秋の紅葉が美しく、
日が暮れるのも忘れてしまう里、
一日中いても飽きない里ということから、
「ひぐらしの里」と呼ばれるようになり、
「日暮里」という言葉が充てられるように
なったそうです。
「日暮里」と呼ばれるようになったのは
江戸時代中期頃からで、
正式に町名となったのは明治22(1889)です。
都市化

日暮里には、久保田藩(秋田藩)佐竹氏の
下屋敷跡がありましたが、
明治末から大正にかけて、
この旧久保田藩佐竹氏の下屋敷跡は
住宅地として開発され、
日暮里は人気のある住宅地となりました。

更に関東大震災を契機に畑は急速に宅地化し、
工場や商店も軒を連ねるようになりました。
特に、ハギレを専門とする
繊維品卸売店が多く見られ、
現在の「日暮里繊維街」の基盤が
作られました。
現在の「日暮里」に当たる地域には
谷中本村の「谷中生姜」を始め、
三河島の漬菜「三河島菜」、
「汐入大根」といった近世からの特産物が
明治・大正期まで作られていましたが、
それらは姿を消していきました。


