
「小正月」(こしょうがつ)とは、
1月1日を中心とした
「大正月」(おおしょうがつ)に対し、
1月15日に行われる行事のことを言います。
この日は、年末の準備から、元旦、松の内と
続いてきた「正月」を締めくくるための
様々な行事が行われます。
小正月とは
古代Chinaから暦が入って来る以前、
日本では「満月の日」を「月の始まりの日」としていました。

旧暦の1月15日は「立春」後の
「望月」(満月のこと)に当たり、
この日を「正月」としていた名残りで、
元日を「大正月」、1月15日を「小正月」と
呼ぶようになりました。
1月 1日を中心に祝う正月が「大正月 」、
1月15日を中心とした正月が「小正月 」です。
なお、「小正月」は地方によっては、
「小年」(こどし) 「若年」(わかどし)
「モチイ」などと言われています。
一般的な「小正月」の日程は、
1月15日、または1月14日~16日の3日間に渡ると
されています。
「小正月」の行事は地域によっては
「大正月」よりも多種多様だとされています。
14日から柳などの木に
小さく切った餅や団子を刺したり、
繭玉を刺して「餅花」を作って飾ったり、
15日の朝には「小豆粥」を食べたり、
正月飾りを焚いたりする
「左義長(どんと焼き)」などを行ったり
します。
餅花(もちばな)
「大正月」が「歳神様を迎える行事」なのに対し、
「小正月」は「豊作祈願」や「家庭的な行事」が
多いのが特徴です。
「大正月」には「門松」を飾りますが、
「小正月」には「餅花」(もちばな)などを飾ります。
「餅花」(もちばな)とは、
豊作を祈り、餅や団子を小さく丸めて
柳などの木の枝につけたものです。
元々は白と赤でしたが、
次第にカラフルなものになりました。
養蚕が盛んな地方では
「繭玉」(まゆだま)とも呼ばれています。
これは「小正月」が豊作の予祝の
大切の行事であるためです。
このことから「花正月」とも呼ばれています。
どんと焼き・左義長

「小正月」の前夜は、
「十四日年越し」(じゅうよっかとしこし)と言って、
年越しの一つに数えます。
「元日」から「小正月」までを
「松の内」と呼んで、
お正月にやって来る年神様の依り代である
松を飾っておく期間とし、
「小正月」で正月行事は終わると考え、
「左義長(どんど焼き)」などを行って
正月行事に区切りを付けました。
女正月
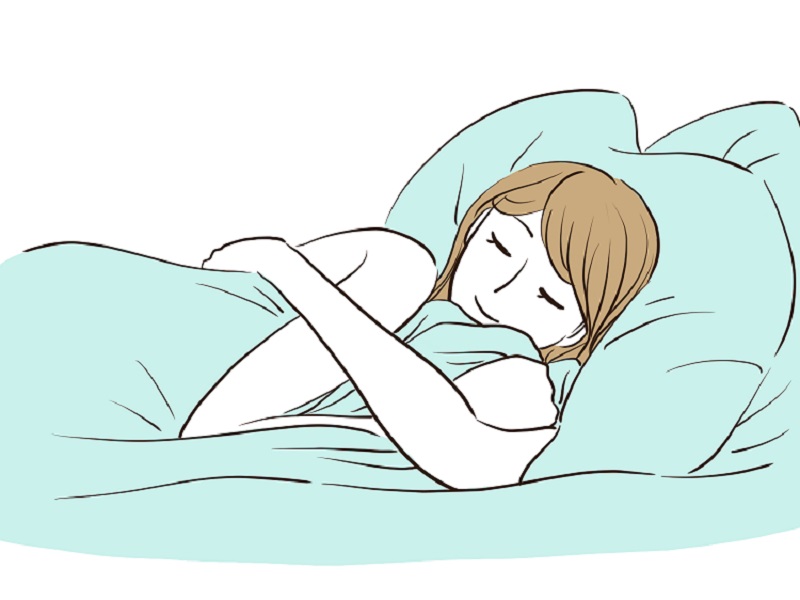
元日を中心とする大正月を
「男正月」と言うのに対して、
十五日の望(満月)の日を中心とする「小正月」は
「女の正月」とも呼ばれ、
松の内に多忙を極めた女性を労う休息日とする
説が一般的です。
<関連事項>






