
「どんど焼き」とは、
1月15日の「小正月」に行われる
全国的の神社や仏閣の「火祭」のことです。
この火祭り行事の名称は地域により様々です。
「どんど焼き」の他にも、
やや変形した「とんど焼き」「どんどん焼き」
「左義長」「サイノカミ」「道祖神祭」
「鬼火焚き」などです。
「左義長」は「三毬杖」(さぎちょう)という
三本の青竹を三つまたに組み、
この周囲に正月の飾り物などを積み上げて、
焚き上げます。
この火祭りを何故「さぎちょう」と呼ぶかに
ついてはいくつかの説があります。
「毬杖」(ぎっちょう)とは、
毬を杖で打ち合うホッケーのような遊びで、
宮廷では徐々に廃れましたが、
鎌倉時代には男の子の代表的な遊びとして、
主に正月に盛んに遊ばれていたようです。
『年中行事絵巻』巻十六には、
正月の場面として、「毬杖」で遊んでいる
子供達が描かれています。
子孫が繁栄することを願うという
縁起を担ぐ遊びだったようです。
江戸時代には遊ばれなくなったため、遊び方も
はっきりとは分からなくなりましたが、
「左義長」は「三毬杖」の意味で、
三本の毬杖を立てて門松などと
一緒に燃やしたのが始まりと言われています。
「書き初め」、古いお札などをお焚き上げ
します。
その煙に乗って歳神様(年神様)が
天上に帰って行くとされています。
また、その火で焼いたお餅などを食べると
無病息災で過ごせると言われています。
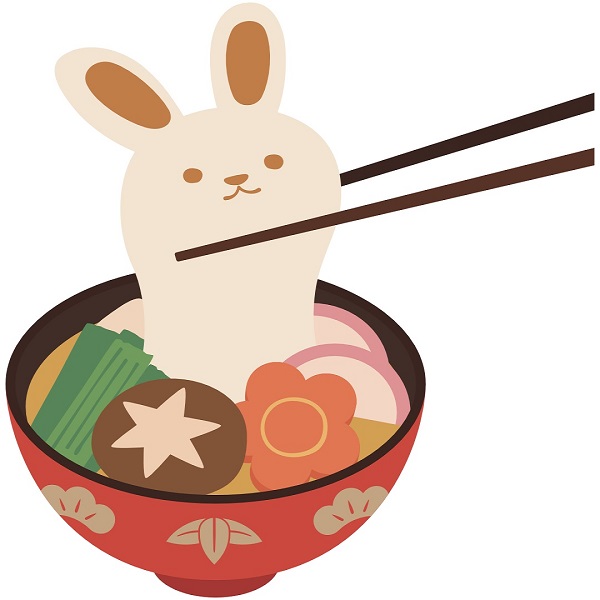
「どんど焼き」には
いろいろな言い伝えがあります。
1.火や煙に当たることで、
一年健康に過ごせるようになる。
2.お餅、団子を食べると虫歯にならない、
健康になる。
3.灰は魔除け、厄除けの力があり、
家の周りに撒くと良い。
4.書き初めを燃やした時の炎が高く上がれば
字が上達する。
「小正月」の日の朝に、
子供達がリヤカーを引いて家々を回り、
「どんど焼き」や「左義長」で燃やす
注連飾りや門松を貰い集めることを
「注連貰ひ」(しめもらい)と言います。
家々で貰うお駄賃もまた
子供達の楽しみの一つでした。
<関連事項>


