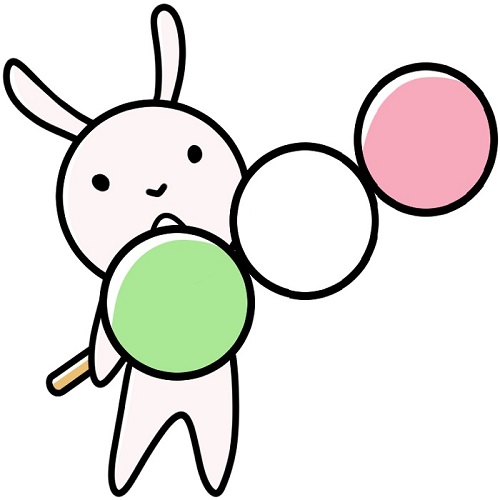
3月16日と11月16日は
「十六団子の日」です。
十六団子の日とは

この日は杵と臼を使って餅つきをし、
餅をつく音で農耕の神様に
山と田を行き来する日であることを
知らせていた日です。
そして出来たお餅は、小さく丸めて
16個の団子を作りお供えします。
田の神様

日本には、古くから山には神様が住んでいると考えられていて、信仰の対象として祀ってきました。
春になると、神様が種子を抱えて
山から里へ降りて来て
「田の神」として農耕を見守ってくれます。
そして収穫が終わる秋になると、
山に戻って「山の神」となって
田畑を見守るという言い伝えがあります。
この思想は「神去来」(かみきょらい)と呼ばれ、
山から降りてくる日が「3月16日」で、
山に帰る日が「11月16日」とされています。
十六団子

昔から、農作業の中で最も重要な農作業の一つ
「田植え」の時期に当たる3月16日には、
豊作を祈願して日本各地で「神迎の儀式」が
執り行われています。

田の神様は、杵が臼を叩く
「ゴン、ゴン」という音を聞きつけて、
山から降りてくると伝えられていることから、
お迎えする日付に因んで、
杵と臼で搗いたお餅で16個の団子を作り、
枡の中に入れて神様にお供えする
慣わしがあり、このお供え物は
「十六団子」と呼ばれています。
「十六団子の行事」は、現在でも、
主に東北地方や北陸地方で行われています。
現在ではさすがに杵臼を使うことは減り、
米粉や片栗粉で作られているようです。
神が山と里を行き来する日や、
団子の作り方や供える場所などについては
地域や家庭によって異なっているのが
実情のようです。
なぜ「16日」なのか?

第54代・仁明天皇(にんみょうてんのう)の御代、
都に疫病が蔓延しました。
江戸時代の百科事典
『和漢三才図会』(わかんさんさいずえ)によると
「承和14(847)年、朝廷に白亀が献上された
ことを吉兆とし、仁明天皇が6月16日に
「嘉祥」と改元、群臣に十六種類の食物を
賜った」とあります。
改元の行われた日付は、
神託に基づいて「六月十六日」となり、
また「十六」に因んだ数の菓子や餅を
神前に供えたことが「嘉祥の儀」という
儀式となって伝えられのでした。

