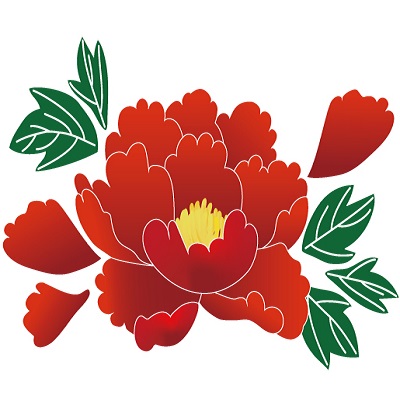
「ぼたんはなさく」
と読みます。
牡丹の花が咲き始める頃となりました。

牡丹は、晩春から初夏にかけて
直径10~20cmの豊麗な花をつけ、
色も紅・淡紅・白・紫など様々です。
牡丹は甘く上品な香りとその格調高い姿から、
唐の時代に「百花の長」として
人気を誇った「牡丹」が
日本に伝わったのは奈良時代です。
初めは薬草として伝わりましたが、
平安時代には
宮廷や寺院で観賞用として栽培され、
江戸期には一般庶民にも栽培が可能になり、
身近な花として親しまれました。
今でも、俳句のテーマや絵画、
着物のモチーフとしてよく登場します。
衣装の文様としては平安時代から用いられ、
室町時代に渡来した「名物裂」にも見られます。
単独で使われる他、組み合わせもあります。
唐草と組み合わせた「牡丹唐草 」、
唐草文に牡丹花とその葉を配した文様。
唐時代にこの文様が完成しました。
正倉院宝物中や名物裂の中に多く見られます。
能の『石橋』(しゃっきょう)をモチーフにした
「唐獅子牡丹 」、
能楽の『石橋』を題材としたもので、
獅子が現れ牡丹の間を舞い戯れ、
天下泰平千秋万歳を祝って、
力強く舞い踊る獅子の姿を表しています。
Chinaの伝説や「胡蝶の夢」から生まれた
「蝶牡丹」、
「胡蝶の夢」とは、荘子が夢の中で胡蝶になり、
自分が胡蝶か、胡蝶が自分か、区別がつかない「物我一体」の境地、または現実と夢とが
区別出来ないことのたとえです。
蝶は長寿の意味を持ち、不死不滅のシンボル
として武士の紋章にもなってきました。
牡丹の花や葉が蟹に似ているユニークな
「蟹牡丹」などがよく知られています。
- 能『石橋』 -
Chinaやインドの仏跡を巡る旅を続けていた
寂昭法師(大江定基)は、Chinaの現在の山西省にある清涼山 の石橋付近に到着しました。
そこに一人の樵(きこり)の少年が現れ、
橋の向こうは文殊菩薩の浄土であること、
この橋は狭く長く、深い谷に掛かり、
人の容易に渡れるものではないこと
[仏道修行の困難を示唆]などを教えてくれます。
そして、ここで待てば奇瑞を見るだろうと告げて
姿を消します。
寂昭法師が待っていると、やがて橋の向こうから文殊の使いである獅子が現われます。
香り高く咲き誇る牡丹の花に戯れ、
獅子舞を舞った後、元の獅子の座、すなわち
文殊菩薩の乗り物に戻ります。









