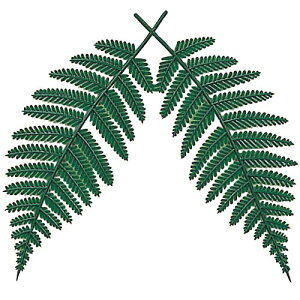その年、亡くなった人のある家で、
12月の第一巳の日、または第二巳の日に
近親者が集まり、お参りを行う行事です。
「巳正月」とは

死者が初めて迎えるお盆を「新盆」(にいぼん)、
初めて迎える正月を「巳正月」(みしょうがつ)
と言います
「巳正月」(みしょうがつ)とは、
12月の「巳の日」を
故人にとっての「正月」として、
故人と家族っが食事を共にすることで、
忌みが明け清らかになって
新春を迎えようとするものと思われます。
「巳正月」の行事は、
四国地方・瀬戸内海の島々、
とりわけ愛媛県の東予・中予地方に
色濃く残る風習です。
この行事は、「仏事」ではなく
お寺との関係はないようで、
あくまでも「民俗習慣」で
「宗教的儀式」ではないようです。
「巳」は生命力の象徴で、再生を表します。
忌明けの慣習が「巳の日」の行われることは、
そうした意味が込められているのかも
しれません。
「巳正月」に行われること
12月の「辰の日」の深夜から「巳の日」、
または「巳の日」から「午の日」にかけて、
真夜中に近親者でお墓参りをします。
墓に「逆さ巻きしめ縄」で墓飾りをし、
「裏白」(うらじろ)を表向きに敷いて、
餅やミカンを供えます。
そして墓前で、
当日搗いたお餅を藁を燃やして炙り、
一切無言でちぎって手渡しはせずに、
刀に刺したり、竹の先に刺して渡して
食べるという儀式です。
この日に餅を食べたり、
この日に搗いた餅を頂いたりすると、
長生きする言われています。
「巳正月」の起源
「巳正月」の起源は諸説あります。
「南北朝の戦い」で
敗走中に亡くなった
「新亡慰霊儀式」説
「巳正月」の起源は、
古くは南北朝の時代まで遡ります。
南北朝の戦いで新田義貞の敗走により、
伊予の国より馳せ参じた兵士が
琵琶湖の北岸の敦賀の木の芽峠付近で
猛烈な吹雪に遭い、多くの凍死者を出しました。
その戦死の知らせが
旧暦10月(新暦12月)の
「巳の日」の「巳の刻」(午前10時頃)に
伊予の故郷まで届けられました。
正月を迎えられなかった無念を慰めるために
執り行った「新亡慰霊儀式」が
「巳正月」の行事として今に伝わったようです。
2.新田義貞の弟葬儀説
南北朝時代、中国・四国地方の総大将として
赴任していた新田義貞の弟・脇屋儀助が
伊予国府で病死した時、
その死を北朝方に悟られないように隠して
葬儀をしたことに因んだという説です。
3.武将たちの出陣の祝い説
戦国時代、愛媛県の中ほどにある
高縄半島(たかなわはんとう)を中心に
勇猛を誇った武将達の出陣の祈りで、
生きて祝えないかもしれない「正月」を
一足早く12月の「巳の日」に祝ったという
説です。
4.村上水軍説
村上水軍の大将が戦で亡くなり、
その亡骸を運ぶ行列は、
「辰」から「巳」にかけての深夜、
大将が亡くなったことを
敵方に知られないように、
一言も発さず粛々と行われた。
その時の様子が慣習として残ったという
説です。
5.朝鮮出兵説
豊臣秀吉の「朝鮮出兵」の帰途、
戦死した兵士を弔うために餅を搗き、
それを朝鮮に向けて供え、
後で皆が竹に餅を刺して食べた
慣習が残ったのだという説です。