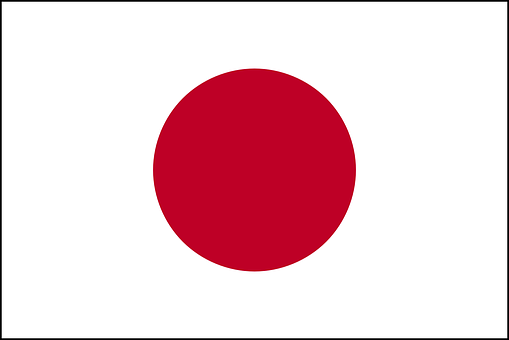11月5日「勅使発遣の儀 」
天皇陛下が、伊勢神宮、神武天皇陵、
昭和天皇陵に使者を派遣するための儀式を
皇居・宮殿で実施。
伊勢神宮では、秋篠宮皇嗣殿下が
皇位継承順位第1位たる
皇嗣となられたことを内外に宣明する
儀式が行われます。
「立皇嗣宣明の儀」が
宮中で執り行われるのに際し、
その当日に勅使が遣わされ
「奉告祭」が行われます。
このお祭りは両正宮に引き続き、
このお祭りは両正宮に引き続き、
全ての宮社で執り行われます。
11月8日「立皇嗣宣明の儀」
秋篠宮皇嗣殿下が皇嗣になったことを
陛下が宣言する中心儀式。(国事行為)
11月8日「朝見の儀」
秋篠宮皇嗣殿下に陛下がお会いになる儀式。
(国事行為)
また、皇室に代々伝わる
皇太子に相伝される太刀「壺切御剣」を
陛下が秋篠宮皇嗣殿下に渡す行事も行われます。
「壺切御剣」」(つぼきりのみつるぎ)は、
皇太子が立太子された証として授けられる
剣です。
「壺切御剣」が授与されるようになったのは
平安時代初期の寛平5(893)年のこと。
当時、「宇多天皇」が
「敦仁親王」(後の醍醐天皇)の立太子に際し、
刀剣を献上したのが始まりです。
これ以降慣例化され、同剣の継承なしに
立太子することは不可能になりました。
現在、伝承される「壺切御剣」は2代目。
初代は康平2(1059)年の宮廷火災で焼失。
2代目の「壺切御剣」は、
「藤原教通」が献上した一振です。
昨年、令和元(2019)年9月26日には、
「行平御剣 伝進の儀」が行われました。
これは、歴代皇太子に受け継がれてきた
御剣「豊後国行平御太刀 」を
皇位継承順位1位の皇嗣となられた
秋篠宮皇嗣殿下に伝えるものです。
御剣は10月22日に皇居・宮殿で行われた
「即位礼正殿の儀」で、
秋篠宮皇嗣殿下が帯剣されていました。
御剣は後鳥羽上皇ゆかりの
豊後国の刀匠が手掛けたとされ、
大正から昭和、平成と皇位継承の度に
歴代の皇太子に伝えられてきた
「由緒物」の一つです。
この日、天皇、皇后両陛下と秋篠宮両殿下は、
装束姿で宮中三殿を参拝し、行事挙行を報告。
両殿下は以後、宮中三殿の殿上に上がって
拝礼なさいます。
但し、皇居などでの記帳は行わず、
両殿下が皇居とお住まいのある
赤坂御用地を移動する際に
儀式的な車列は組まないそうです。
また、両殿下が報告のため
伊勢神宮、神武天皇陵、昭和天皇の武蔵野陵を参拝する日程は今のところ未定。