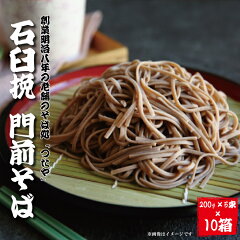「初午」(はつうま)とは、
2月最初の「午の日」のことで、
稲荷神のお祭りが行われる日です。
稲がなることを意味する「稲生り 」から、
五穀豊穣や商売繁盛、家内安全を祈願して、
各地の稲荷神社でお祭りが行われます。
令和6(2024)年の「初午」は2月12日で、
「二の午」は2月24日です。
「初午」とは

2月に初めて迎える午の日を
「初午」(はつうま)と言います。
この日、京都の「伏見稲荷大社」を始め、
全国各地の稲荷神社や稲荷の祠(ほこら)では
お祭りが行われます。

この日にお参りすることを
「初午詣」(はつうまもうで)とか「福参り」と
言います。
また稲荷の祭りの日を待っていた
庶民の心情から、「稲荷待ち」とも言います。
由来

約1300年前、奈良時代の
和銅4(711)年の2月11日(または9日)の初午の日、
京都の「伏見稲荷大社」の祭神が、
午 [馬]に乗って伊奈利山(いなりやま)に
降臨したという言い伝えに由来しています。
この神様は穀物を司る神様で、
稲荷の文字は、稲荷は「稲成、稲生」(いねなり)が
転じたものというだけでなく、
五穀の中でも特に稲を司る
「倉稲魂」(うかのみたま)を祀っていますから、
春の農事に先駆けての豊作を祈る祭りで、
各地に稲荷神社が広まっていきました。
京都・伏見稲荷大社の主祭神で、
一般に「稲荷神(お稲荷さん)」として広く
信仰されています。
農耕の神・商工業の神・商売繁盛の神としても信仰されていて、全国の稲荷神社で祀られています。
名前の「ウカ」は穀物・食物の意味で、
「穀物の神」様です。
『古事記』では宇迦之御魂神、
『日本書紀』では倉稲魂尊と表記されています。
須佐之男命と神大市比売(大山津見神の娘)との間に生まれ、大年神の妹神とされています。
別名、御饌津神 、宇賀御魂命 。
なお神道系の総本社は京都の「伏見稲荷」で、
仏教系の総本山は「豊川稲荷」になります。
中世に入って商工業が盛んになると、
商売繁盛の神様にもなります。
江戸時代には、
「伏見稲荷大社」の御分霊を授かり
「正一位稲荷大明神」を勧請することが
盛んになり、全国に広まりました。
今では、商売繁盛、産業興隆、
家内安全、交通安全、芸能上達など
様々な幸福をもたらす神として信仰を集め、
全国各地には稲荷神社は3万社あり、
全国の神社の三分の一を占めます。
「正一位稲荷大明神」
神道における神様に授けられる
「位階」(位の高さや階級)を「神階」と言います。
正六位から正一位までの15階あります。
正一位の神社には、「松尾大社」「上賀茂神社」
「下鴨神社」「春日大社」「石上神宮」「枚岡神社」
「香取神宮」「鹿島神宮」「日吉大社」そして
「伏見稲荷大社」があります。
天長4(827)年に、淳和天皇が
突然病気で臥せられた際、病の原因を占うと、
前年建立した東寺の五重塔の用材として
伏見稲荷山の神木を伐った祟りだと分かりました。
そこで天皇はすぐに稲荷山に使者を遣わして、
それまで位階のなかった稲荷神に「従五位下」の
神階を授け、怒りを鎮められました。
更に天慶5(942)年、朱雀天皇より最高位の
「正一位」の神階を授かったことにより、
伏見稲荷大社の祭神「宇迦之御魂神 」は
「正一位稲荷大明神」と呼ばれるようになりました。
鎌倉時代、伏見稲荷大社を訪れた後鳥羽天皇が、
分霊先でも「正一位」を名乗ることを許可した
ことから、以後、伏見稲荷大社は「稲荷勧請」際、
全て「正一位」の神階を付けて分神しました。
その結果、全国の勧請を受けた稲荷神社のほとんど
全部が「正一位稲荷大明神」を名乗ることになり、
「正一位」は稲荷社の代名詞のようになりました。
縁起物の「しるしの杉」
「初午」の頃に、
商売繁盛・家内安全のお守りとして
多くの参拝者が縁起物の「しるしの杉」を
買い求めていきます。
平安中期以降、紀州の熊野詣が盛んとなり、
その往き帰りには、
必ず稲荷社に参詣するのが習わしとなっていて、
その際には、稲荷社の杉の小枝である
「しるしの杉」をいただいて、身体のどこかに
つけることが一般化していました。
本来はこの杉を庭に植え、根付かせるのが
習わしだそうですが、
現在は「御幣」として飾るものとなっています。
二の午・三の午
「初午祭」は、
旧暦で数えて「初午」の日に行う場合と、
新暦で数えた「初午」の日に行う場合が
あります。
また2月ではなく、
奄美大島のように「4月初午」をいう所や
「11月初午」をする所もあります。
また「午の日」は十二支に基づいているため、
2月中に2回目の「午の日」、3回目の「午の日」が
巡ってくることがあります。
この場合、2回目の午の日を「二の午」、
3回目の午の日を「三の午」と呼びます。
これらの日にも祭礼を行う地方や、
「二の午」もしくは「三の午」のみ
祭礼を行う地方もあります。
なお「三の午」のある年は出火の危険があるとも言われていますので、火の用心!
馬に因んだお祭り

「稲荷信仰」とは別に、
馬に因んだお祭りをするところもあります。
東北地方や東海地方には、
馬(午)の守護神「蒼前様」(そうぜんさま)や
「馬頭観音」にお参りする所があります。
長野・山梨・埼玉などの養蚕地帯では、
「初午」に蚕の神様を祀る行事も行われます。
蚕神である「蚕影様」(こかげさま)とか
「オシラ様」などの祭りをしたり、
繭玉を作って屋内外の神に供えたりしました。
実は、「蚕」と「馬」は深い関係があり、
前述の「オシラ様」は蚕神だけでなく、
馬の神とも言われています。
東北地方には、この「オシラ様」の成立に
まつわる悲恋譚が伝わっています。
『聴耳草紙』にはこの後日譚(ごじつだん)があり
天に飛んだ娘は両親の夢枕に立ち、
臼の中の蚕虫を桑の葉で飼うことを教え、
絹糸を産ませ、それが「養蚕」(ようさん)の由来になったというものです。
火の用心

「初午」の日には、
消防団員が各家庭を回り、
火の用心を呼びかけたり、
火の用心のお札を配る地域があります。
また、「この日は茶を飲まない」
「風呂を沸かさない」など、
火を扱うこと自体避けようとする地域や、
家に水をかけるなど火防の行事をする地域も
多くあります。

「初午」に雨が降らないと火に祟られるとか、
「初午」の早い年は火事が多くなる、
「三の午」のある年は出火の危険があるとも
言われています。
この日に火の用心を呼びかけるのは、
稲荷神のお使いと言われ「キツネ」にまつわる
言い伝えがあるからです。
1匹の女キツネを巡って
2匹の男キツネが争いを繰り広げ、
負けた方の男キツネが村に火を放ち、
村人を困らせたというものです。
確かにこれらの話は俗信かもしれません。
ですが、この時期は乾燥していて風も強い頃。
是非、火の取り扱いにも気を付けたいものです。
日本各地の初午祭
この日は、全国にある稲荷神社で
お祭りが行われます。
稲荷神社では「正一位稲荷大明神」と書いた
幟(のぼり)やを立て、
お神酒、赤飯、油揚げなどをお供えします。
屋敷に祀る稲荷祭祀の位置は、
戌亥(西北)の隅です。
稲荷神社の総本社・伏見稲荷大社の初午大祭【京都府】
京都伏見にある「伏見稲荷大社」は、
全国にある稲荷神社の総本宮です。
参道にずらりと並ぶ「千本鳥居」で
知られています。
朱塗りの鳥居が連なっているのは、
願い事が「通る」「通った」などの意味から、
心願成就の祈念や成就の感謝を込めて
鳥居を奉納する習慣が
江戸時代以降に広がったため。
ですから「願いが通りますように」と
気持ちを込めて鳥居を潜って下さい。
そして神社の楼門前では、
神様のお使い(神使)であるキツネの像が出迎えてくれます。
伏見稲荷大社の「初午大祭」は
「福参り(福詣り)」などとも呼ばれ、
多くの人が訪れて商売繁盛などを祈願します。
社頭で参拝者に授与されている
「しるしの杉」は伏見稲荷大社のご神木である
杉を用いたお守りです。
商売繁盛・家内安全を願いつつ、
玄関や神棚に飾ります。
- 京都府京都市伏見区深草薮之内町68
笠間稲荷神社の初午祭【茨城県】
日本三大稲荷の一つ「笠間稲荷神社」では
新暦と旧暦の2月に行われています。
- 茨城県笠間市笠間1
祐徳稲荷神社の初午祭【佐賀県】
佐賀県鹿島市にある、日本三大稲荷の一つ
「祐徳稲荷神社」の「初午祭」は、
稲荷大神様が御鎮座されたご縁日に
行われます。
深夜0時より商売繁昌なども祈祷が開始され、
一日中賑わいます。
境内では、「平戸神楽」(ひらどかぐら)、
「面浮立」(めんぶりゅう)、
「一声浮立」(いっせいぶりゅう)の他、
民謡などが奉納されます。
- 佐賀県鹿島市古枝乙1855
冠稲荷神社の初午大祭【群馬県】
日本一の木瓜で知られ、
源氏にゆかりが深い神社としても知られる
「冠稲荷神社」の「初午大祭」は、
旧暦の初午に近い3月、
群馬県指定天然記念物「冠稲荷のボケ」の
花の咲く頃に毎年開催されています。
ランドセルなどのお祓いをしてもらえる
「初午開運安全幸福祈祷」や
「義経公・義貞公 厄除稚児行列」
「細谷冠稲荷獅子舞」などが行われ、
桜の開花中は、ライトアップされた夜桜も
楽しめます。
- 群馬県太田市細谷町1
鹿児島神宮の初午祭【鹿児島県】
海幸彦・山幸彦 伝承の地
「鹿児島神宮」の「初午祭」は
旧暦の1月18日に近い次の日曜日に
開催されます。
鈴かけ馬の踊りと踊り連の舞を
鹿児島神宮に奉納し、
牛馬を始めとした家畜の安全や多産、
五穀豊穣・厄除け・家内安全を祈願します。
歴史ある伝統行事として
国の無形民族文化財にも指定されています。
- 鹿児島県霧島市隼人町内2496-1
豊川稲荷東京別院の「初午串札」【東京都】
白い狐に乗る仏法の守護神・
荼枳尼天(だきにてん)を祀る
豊川稲荷東京別院では、
「初午串札」を授与しています。
初午限定の御朱印も人気です。
- 東京都港区元赤坂1-4-7
王子稲荷神社・凧市【東京都】
民話『王子の狐火』や
落語『王子の狐』でも有名な
「王子稲荷神社」では、毎年2月の午の日に
江戸時代からの風物詩である凧市が
開催されます。
江戸時代、度々大火に見舞われたことから、
風を切って上る凧を火事除けのお守りにと、
民衆が王子稲荷神社の奴凧を
「火防の凧」(ひぶせのたこ)として
買い求めたのが始まりです。
凧市はこの「火防の凧」を求める多くの人で
賑わいます。
また屋台が100店程も並び、
子供達も楽しめる場所となっています。
王子稲荷神社
- 東京都北区岸町1丁目12−26
三輪里稲荷神社の「こんにゃくの護符」【東京都】
三輪里稲荷神社では、初午の日に
「こんにゃく御符」授与していることから、
別名「こんにゃく稲荷」と呼ばれ、
親しまれています。
この「こんにゃく護符」を煎じて服用すれば、
喉や風邪の病に神験あらたかとされることに
由来します。
「こんにゃく御符」は竹串ごと煎じて、
そのお湯を服用します。
- 東京都墨田区八広3丁目6−13
関連記事