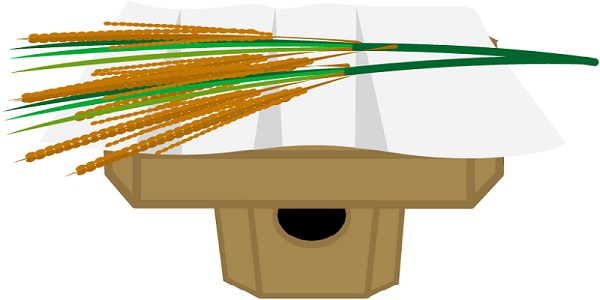
神嘗祭(かんなめさい)
「神嘗祭」(かんなめさい)は、
10月17日に宮中と伊勢神宮で行われます。
今年穫れた作物、新穀を
神様にお納めする意味を持ちます。
稲の初穂(田で初めて穫れた稲穂)を
船に載せて伊勢神宮に奉納する、
「初穂曳き」(はつほひき)。
また新穀で新酒を作り、
御饌(みけ)や神酒(みけ)を供え、
五穀豊穣に感謝するのが習わしです。
元は、旧暦9月の乙卯の日に始まったと
言われています。
(外宮:15、16日 / 内宮:16、17日)
新嘗祭(にいなめさい)
「新嘗祭」は11月23日に宮中で行われます。
「新嘗」と言うのは、
今年穫れた新しい穀物のことです。
神様に天皇が新穀を奉り、
その新穀を神様と共にいただく習わしです。
新米を炊き、
新酒の白米の酒「白酒」(しろき)や
赤米や黒米の酒「黒酒」(くろき)を
いただくのは、
共食の意味合いを持つ大事な祭事です。
かつては、旧暦11月の第二の卯の日に行われていました。
「新嘗祭」は、
旧暦ではおよそ「冬至」の頃に在り、
一年の大きな節目でした。
大嘗祭
(だいじょうさい/おおなめのまつり)
天皇が即位後初めて行う新嘗祭を、「大嘗祭」と言います。
この「大嘗祭」と経て初めて正式に、
践祚(天使の位を受け継ぐこと)された天皇となるそうです。
相嘗祭(あいなめのまつり)
昔は、旧暦11月の最初の卯の日に、
稲の収穫を祝う「相嘗祭」が行われていた
そうです。
新穀を神社に捧げ、神々に供えました。

