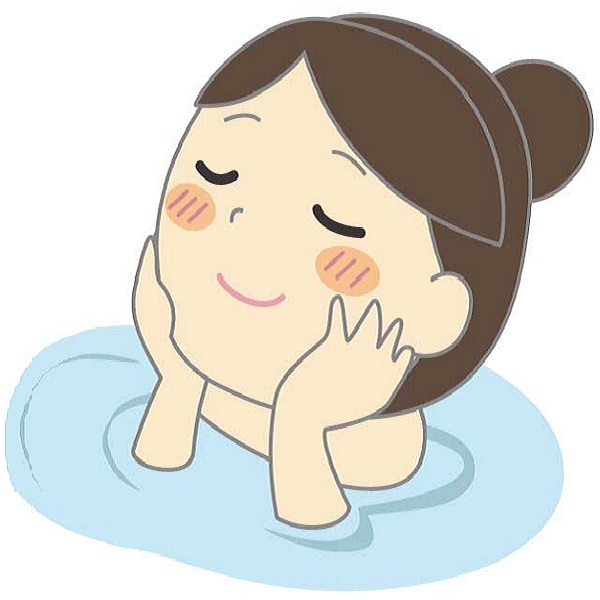一年の最後の日を「大晦日」(おおみそか)
または「大晦」(おおつごもり)と言います。
神社では「大祓」(おおはらえ)と言って
人形(ひとがた)に託して罪穢を流し、
寺院では百八煩悩の鐘を撞き鳴らします。
大晦日(おおみそか)
「晦」(つごもり)とは、
「月が隠れる日」すなわち「月隠」(つきごもり)が
訛ったもので、毎月の末日を指します。
12月末日の「晦日」は
「1年の最後の特別な末日」なので、
末日を表す言葉に「大」を付けて
「大晦日」とか「大晦」と言います。
年越えの祓、大祓い
6月の「夏越の祓」と対をなし、
12月31日、新年を明日に控える大晦日の日に、
年神様をお迎えするために、
穢れを祓い心身を清める神事が、
「年越しの祓」(としこえのはらえ)または、
「大祓い」(おおはらい)です。
平安時代から行われていたと言われ、
「大晦日」には1年の間に受けた
罪や穢れ(けがれ)を祓うために
宮中や全国の神社で執り行われています。
真っ白い紙で出来た「人形」(ひとがた)を持ち、
自分の体を撫でる仕草をして、
フッと息を吹きかけます。
そうする事によって、
穢れを人形が引き受けてくれたものとして、
その人形を川や海に流したり火に焚いて、
健康や長寿、厄除けを祈願します。
除夜(じょや)
「除夜」(じょや)とは、12月31日の夜、
一年の最後の夜のことです。
「年の夜」(としのよ)、「大年」(おおとし)、
「年越し」などとも言います。
日本ではかつて、一日の終わりが日没時とされ、
日没以降はもう明日とされたことから、
大晦日の日が暮れた「除夜」は既に新年に属し、
来臨する年神をまつる神聖な夜でした。
このため大晦日の夜は眠らないで、
神社では篝火が焚かれ、参籠が行われ、
一般家庭でも、家に籠って眠らずに
夜通し祈願する「年籠り」(としごもり)をして
新しい年を迎えることが一般的でした。
「年の火」(としのひ)
大晦日の夜、神社や寺、家の庭で榾火(ほたび)
などを焚いて、神事や仏事に使ってきたものを燃やすこと。火には清めの意味がありました。
「年越しとんど」と呼ぶ地域もあることから、
「左義長」と通じるものと思われます。
「年守る」
大晦日の夜、眠らずに新しい年を迎えること。
家族が一部屋に集まって話をしたりして、
年の明けるのを待ったり、あるいは寺や神社に集まって、年の火を守りながら新年を迎えました。
この夜に早く寝ると、
「白髪になる」「シワが寄る」などの
俗信がありました。
どうしても眠くなったら「寝る」ではなく
「稲積む」(いねつむ)と言うと、
魔力から逃れられるそうです。
時代の流れとともに
「年籠り」の風習は形が変わり、
元日に行われていたお参りが残って、
現在の「初詣」に繋がっています。
大晦日の4つの風習
「掃納」(はきおさめ)⇨ 掃除をする



既に「煤払い」は済ませていますが、
新しい年を迎えるために、
大晦日に、「掃き納め」(はきおさめ)と言って
その年最後の掃き掃除をします。
師走の間にあれこれしてきた
正月の準備の締めくくりの意味合いもあり、
掃除をしている間に、正月を迎える心の準備が
整っていきます。
新年を気持ちよく迎えるためというだけでなく、
元旦に掃除をしないためでもあります。
元旦に掃除をすると、
神様まで掃き出してしまうため、
元旦に掃除をしないという話があるのです。
「年取りの飯」(としとりのめし)⇨ 家族揃って過ごす

昔は「数え年」だったので、
正月を迎えると、
皆一緒に一歳、歳を取るとされていました。
日が沈むと新しい一日が始まると
考えられていたので、
大晦日の夜には、新しい年の始まりと
歳を取れたことを祝うために、
「年取りの飯」または「年越し料理」と言って
普段は食べられないような豪華な食事を
家族揃って食べました。
このご馳走のことを、
「お節」(おせち)と呼んだのが、
やがて正月に頂く「重箱料理」を
「お節」(おせち)と言うようになりました。
「年越し蕎麦」を食べる
大晦日の夜には、
「年越し蕎麦」を食べる風習があり、
江戸時代から人々の間で定着し、
今では日本の文化になっています。
「晦日そば」「つごもりそば」「運気そば」とも呼ばれています。
「年越」(としこし)
大晦日から元日へと年が移ること、
また、その間の行事や風習を言います。
「除夜の鐘」を聞いたり、
「年越し蕎麦」を食べたりします。
これは、正月にやって来る
年神様を迎えるために心身を清め、
一晩中起きていた古い慣わしの名残りです。
「立春」の前夜である「節分」の夜も
「年越」と言います。
「年の湯」(としのゆ)⇨ 風呂に入る
大晦日に入る今年最後のお風呂です。
「年の垢」とも言うように、
ゆっくりと除夜の湯に浸かって、
一年の垢を落とすことを
「年の湯」(としのゆ)と言います。
かつては入浴は日常的ではなかったので、
大晦日の入浴は、新年を迎えるための
禊(みそぎ)の意味もあったと考えられます。
「除夜の鐘」を聞く
大晦日の夜、年が変わる元旦にかけて
全国のお寺では「除夜の鐘」が鳴り響きます。
鐘の音は全部で108回。
この数字は人間の煩悩の数とされています。
最後の1回は、年が明けてから撞くのが一般的で
新しい年が煩悩に煩わされないようにとの
願いが込められているそうです。
<関連記事>