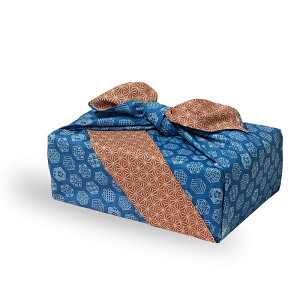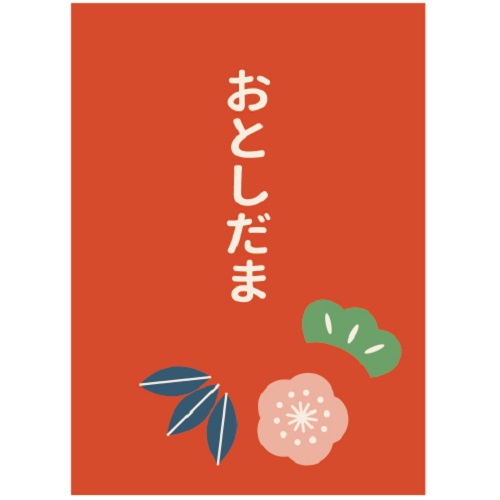正月三が日に、
ご挨拶に伺うことを「お年始」(おねんし)、
その時に贈るものを「お年賀」(おねんが)と
言います。

「お年始」は、元々は、農村部で行なわれてきた
お正月の行事に由来します。
当時は「年賀」(ねんが)とも呼ばれ、
分家が本家に集まって、「年神様」を祀って
新年を祝っていました。

それが江戸時代に入ると、商人が得意先に
新年の挨拶に出掛ける習慣が生まれした。
それが現代にも続き、
「年始回り」(ねんしまわり)と呼ばれるようになり、
今では親族だけでなく、仲人や上司など、
お世話になっている相手の家に挨拶をする
行事へと変化しました。
古来、「元日」は家に籠って年神様を待つ日で、
外出はしない日なので、「元日」は避けるのが
基本です。
「お年始」は2日以降の
「松の内」に済ませるのが一般的です
普通は7日頃までですが、
地域によっては10日や15日までの場合も
ありますのでご注意下さい。
<礼者>(れいじゃ)
正月三が日に威儀を正して、知人や親戚宅などを
年賀に回り歩く人のことを「礼者」と言います。
更にその年最初の賀客が「初礼者」と言い、
門先だけで辞する賀客が「門礼者」と言います。
年始客の多い所では、玄関に礼帳や名刺受けが
置かれています。
<礼受>(れいうけ)
正月三が日の間、年賀の客を玄関先で抑えて、
その祝辞を受けること、またその人を指します。
「門礼」(かどれい)の賀客に応対することです。
手あぶりの火鉢を用意する家もあります。
挨拶することが目的ですから、
長居はしません。
一般的には、
昼食が終わった頃から夕食支度前の時間帯、
大体は午後1時から2時頃に訪問するのが
常識的であり良いとされています。
また、お年始に行く際は、
必ず前もって先方に連絡をして、
訪問しても良い時間を聞いておきましょう。
お正月は、来客や出掛けることも多いため、
都合を聞いておかないと、先方に迷惑を掛けることになります。


「お年賀」には、
縁起担ぎの品や十二支に因んだものなど、
お正月らしいものを用意します。
表書きは「御年賀」とし、
松の内を過ぎた場合は「寒中見舞い」とします。
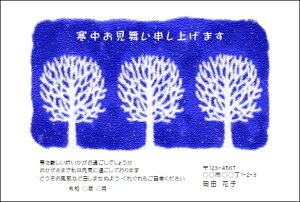
現在では、お年賀は
「日頃、お世話になっている方への感謝」と
「今後のお付き合いへの願い」
を込めて贈るものです。
そのため、お年賀を贈る相手は
実家の両親を始め、お世話になっている親戚や
勤め先の上司などが考えられます。
また、結婚された方は仲人にも
忘れずに贈りましょう。