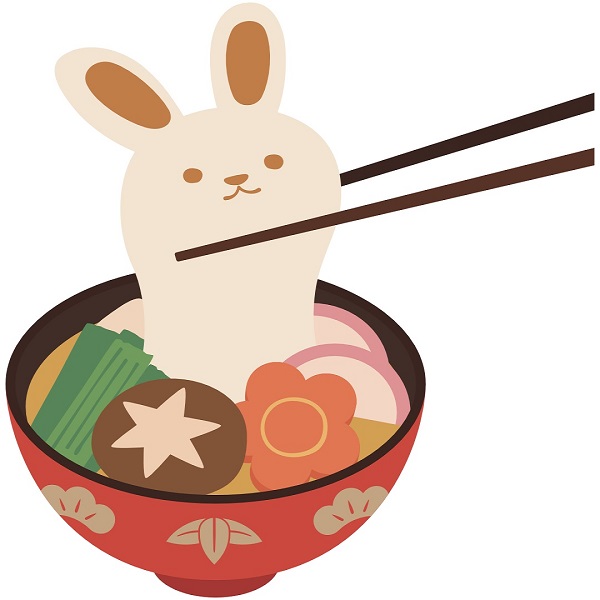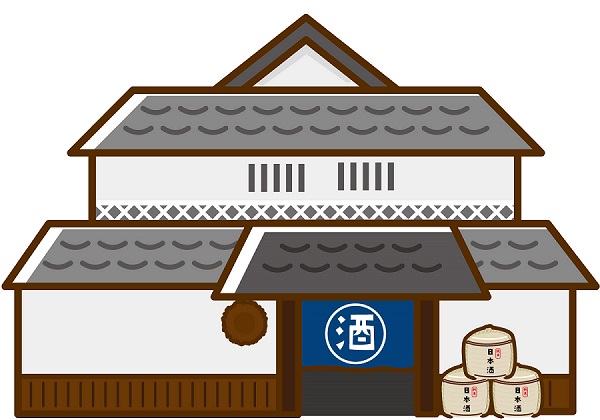
年末に閉じた蔵を
新年になって初めて開ける日のことで、
江戸時代には、諸大名家では「米蔵」を、
商家では2日の「初荷」の出入りで
「蔵」を開くことをそれぞれ、
新年に吉日を選んで「蔵」を開く儀式を
行いました。
ところが20日が三代将軍である徳川家光の
月命日になったことで、
「鏡開き」が1月20日から1月11日になると、
1月11日が旧暦で「大安」になることもあって、
「蔵開き」もそれに合わせて
「1月11日」に行われるようになりました。
商家では、この日は神主さんを呼んで
商売繁盛を祈願し、
食しました。
ところで、日本酒が好きな人なら、
「蔵開き」というと酒蔵の「蔵開き」を
思い浮かべるかもしれません。
酒蔵の「蔵開き」は
年始の「蔵開き」とは違い、
日本酒の造り始め
もしくは造り終わりに行われるもので、
普段は見ることの出来ない酒蔵の中に入って、
お酒を造っている工程を見学したり、
発酵中のもろみの甘い香りを堪能したり、
甘酒の振る舞いがあったり、
絞りたてのお酒をいただいたりと、
お祭りのような行事です。