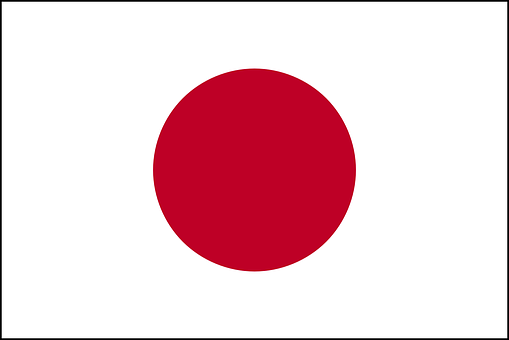2月11日は「建国記念の日」(けんこくきねんのひ)
です。
「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として、
昭和41(1966)年に定められました。
「2月11日」という日付は、
初代・神武天皇が現在の奈良県の
橿原の宮にて御即位された日である、
「旧暦」の紀元前660年1月1日を
「新暦」に換算した日付です。
「建国記念の日」はかつては
「紀元節」(きげんせつ)と呼ばれていました。
近代国家の仲間入りを果たした明治時代、
日本の国の起こりを祝う日が必要だという
声が高まったことから
明治6(1873)年に制定されたのです。
なお「紀元節」は梅が咲き始める頃なので、
「梅花節」「梅佳節」とも呼ばれました。
「紀元節」には、
宮中皇霊殿(きゅうちゅうこうれいでん)で
天皇親祭の祭儀が行われた他、
全国の神社で「紀元節祭」が華々しく
行われました。
小学校では、天皇皇后の御真影(写真)に
対する最敬礼と万歳奉祝、
校長による『教育勅語』の奉読、
唱歌『紀元節』を斉唱して、
紅白のまんじゅうを持ち帰りました。
庶民の間でも「建国祭」の祭典が行われました。
しかし第二次世界大戦後の昭和23(1948)年、
「紀元節を認めることで、天皇を中心として
日本人の団結力が高まるのではないか」
というGHQの懸念により
「紀元節」は廃止されることになります。
それでも国民の間で、
「紀元節」復活の動きが高まり、
9回の議案提出・廃案を経て、
ようやく昭和41(1966)年に「建国記念の日」は
国民の祝日に追加されました。
成立までに時間がかかった背景には、
① 「紀元節」の復活に意義を唱える
野党などからの反発
② 現在の歴史学では
神武天皇の存在に確証がなく、
「正確な起源が分かっていないので
建国記念日など定められない」とする
学者からの意見が多くあった
ことがあげられます。
最終的には、史実に基づく
建国された日とは関係なく、
単に建国されたという事実そのものを
記念する日だからと言うことで、
「建国記念日」ではなく「建国記念の日」
となりました。
現在も各地の神社が、
健康を祝うお祭りを開いています。