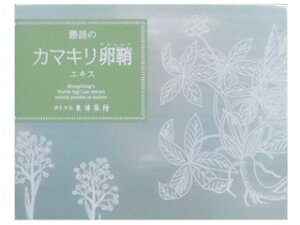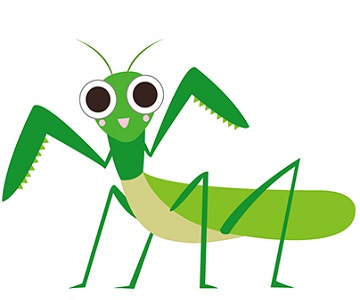
「かまきりしょうず」
と読みます。
「蟷螂(かまきり)が卵から孵(かえ)る頃」
となりました。
蟷螂は、秋に粘液を泡立てて作った
卵鞘(らんしょう)の中に
たくさんの卵を産み付けます。
その卵鞘の中の卵が孵化して
数百匹の小さな蟷螂が次々と現われ始めます。
ただ成虫して生き延びるのは2、3匹だそうです。
前足の鎌がトレードマークのカマキリは、
「鎌で切る」ことから「鎌切り」(かまきり)に
なったと言われています。
その足の動きは素早くて、
一瞬のうちに虫を捕まえてしまいます。
そのためでしょうか、
「蝿取り虫」とか「疣(いぼ)むしり」などとも
呼ばれています。

前足を合わせて、目の前に獲物が現れるのを
身じろぎもせずにじっと待ち伏せする姿が、
まるで神仏でも祈っているように見えるので、
「拝み虫」とも呼ばれます。
稲や野菜には手をつけず、
農作物につく害虫を捕食するカマキリは、
昔から「益虫」として頼りにされてきました。
カマキリがいる場所には、
捕食される生物がいるということでもある
ため、カマキリは豊かさの象徴として、
カマキリの卵嚢を大事に保護する農家さんも
います。

京都の夏の風物詩「祇園祭」では、
カマキリがカマを振り上げ、
御所車の車輪が動くからくりが施されている
「蟷螂山」(とうろうやま)、別名「カマキリ山」
という山車があります。
「祇園祭」では、カマキリは神の能力を持ち、
神の使者として崇められているのです。