
「かみなりすなわちこえをはっす」
と読みます。
春の訪れとともに、恵みの雨を呼ぶ雷が
鳴り始める頃です。
対になっています。
春雷(しゅんらい)

春に聞く雷のことで、
「春の雷」(はるのらい)とも言います。
春の雷である「春雷」(しゅんらい)と
夏の雷である「熱雷」(ねつらい)とでは、
成り立ちが違います。

夏の雷「熱雷」(ねつらい)は、
熱せられた上昇気流によって形成された
「積乱雲」による雷です。
一方「春雷」(しゅんらい)は、
大陸から南下する寒冷気団の先頭にある
寒冷前線が通過する時に発生する雷で、
気象用語では「界雷」(かいらい)と言います。
「春雷」には、夏の雷「熱雷」に見られる
荒々しさ、厳しさはありませんが、
この雷雨が雹(ひょう)を伴うと、
農作物に被害を与えることもあるので、
注意が必要です。

「春の雹」(はるのひょう)
寒冷前線の付近に積乱雲が発達して雷が発生し、更にその発達が進むと「雹」(ひょう)を降らせます。「雹」(ひょう)は雷雨を伴って降る不透明な氷塊で、
夏に降ることが多いのですが、春にも小粒なものが細雨に伴って降ることがあります。
「初雷」と「初稲妻」

「立春」後、初めて聞く雷のことを
「初雷」(はつらい)と言います。
春の訪れを知らせ、
冬眠していた地中の虫達が
雷鳴に驚いて目覚めるという意味から
「虫出しの雷」とも呼ばれています。
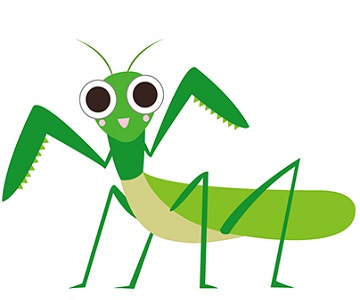
ところで「立春」後、
初めて見る稲妻のことを
「初稲妻」(はついなづま)と言います。
「雷」と「稲妻」は
同じような意味に思えますが、
実はその意味には明確な違いがあります。
簡単に言うと、雷は「音と光」、
稲妻は「光自体」を意味します。

黒い雲が広がった真っ暗な空を見ていると、
まずピカッと光り、
その後にゴロゴロと雷鳴を轟かせます。
この最初の光だけが「稲妻」で、
音を伴わないのが特徴です。
「ゴロゴロ」と雷鳴を轟かせながら放電する
自然現象のことを「雷」と呼びます。

因みに英語では、
「雷」を「サンダー(Thunder)」、
「稲妻」を「ライトニング(lightning)」と
それぞれ呼称します。
雷雲の内部で正と負の雷位差が高まり、あるところまでくると中間にある空気の絶縁が破れて火花放電が起きる。多く屈折して見える。
秋に多く見られ、単に稲妻と言えば秋の季語である。
「雷の多い年は豊作になる」

元々、雷は「神鳴り」と表され、
その激しい雷鳴は神様が鳴らしているものと
考えられていました。
これは日本だけでなく、
世界各国でも「空・天=神」と解釈され、
雷は神様の仕業とした記録が残っています。

昔から「雷が多い年は豊作になる」と
言われていて、
「稲妻」は稲が実る時期に多発することから、
この名が付けられたと言われています。
これらは単なる言い伝えではなく、
雷の電流が大気中の窒素を土壌に固着させ、
作物に対して良い影響を与えることは、
科学的にも立証されています。

植物の成長に欠かせない三大要素は、
「窒素(N)」「リン酸(P)」「カリウム(K)」
です。
これらを外部からバランスよく施すことが、
稲の収穫量を上げる上で大切になります。
雷の放電現象によって、
空気中の「酸素」や「窒素」が
イオン化されます。
これらのイオンが雨に溶け込んで、
大地に天然の肥料を提供してくれます。
空気の成分の大部分は「窒素」なので、
天然水で程良く希釈された
窒素肥料が十分に供給されるので、
豊作となるのだそうです。
なお、それぞれ語源や意味が違うことから、
「雷」は「夏」を表す季語、
「稲妻」は「秋」を表す季語というように
使い分けられています。


